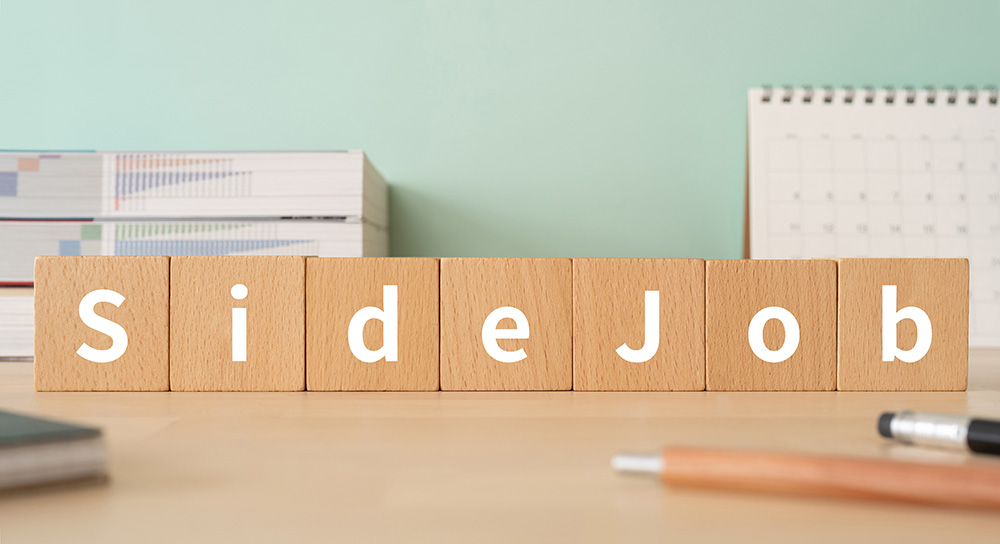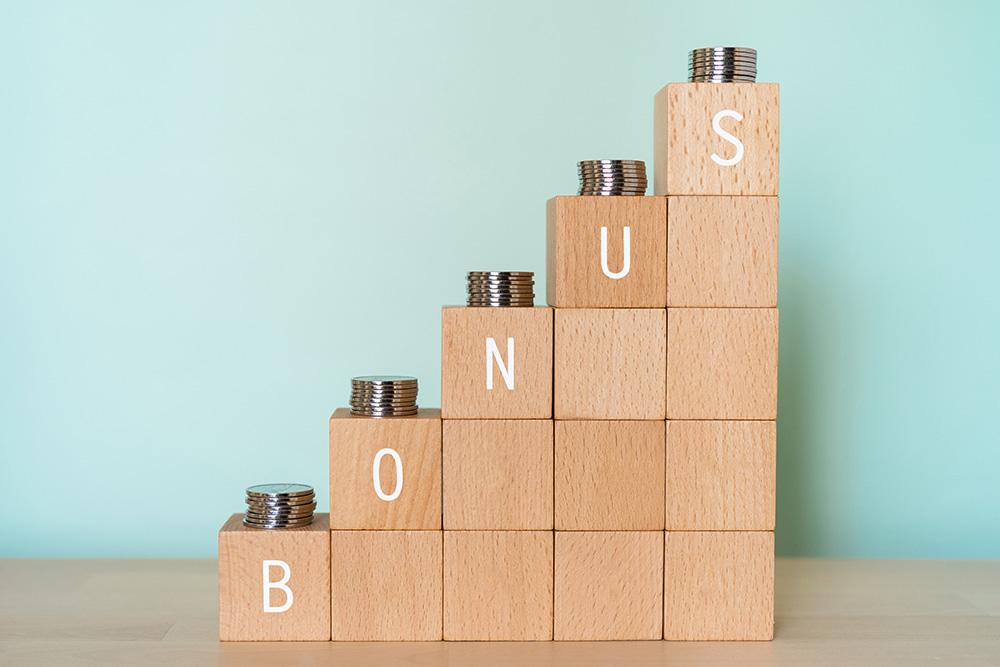人事コンテンツ
目標管理(MBO)とは?設定するメリットや運用するポイントを解説!
2023/2/21

従業員の成長と企業の成長のための方法として目標管理(MBO)が注目されています。今の社会は、上司が指示をして動く従業員だけでは生き抜くことができません。従業員が高いモチベーションで能動的に仕事ができる環境を構築し、個人の成長が企業の成長につながる組織作りをしなければならないのです。
当記事では、目標管理(MBO)の概要から導入するメリット、導入時の注意点について解説していきます。この記事を読むことで、目標管理(MBO)の重要性を理解することができ、自社に合ったMBO制度の構築を検討できるようになります。
多くの組織でジョブ型成果主義人事制度と目標管理制度の導入・定着を手掛けてきたプロフェッショナルのコンサルタントが、目標管理制度の基本的な考え方から効果の出る実践的運用方法までを、わかりやすく解説しています。
既に目標管理制度を導入している企業はもちろん、これから目標管理制度の導入を検討している企業に役立つ内容ですので、是非ご活用ください。
⇒「目標管理制度の基本的な考え方から効果の出る実践的運用方法の解説資料」を無料でダウンロード
目標管理(MBO)とは?
目標管理(MBO)は「Management by Objectives」の略語であり、マネジメントの父と言われている経営学者のピーター・ドラッカーが提唱した理論です。
目標管理とは組織のマネジメント手法の一つであり、会社で働く様々な立場の従業員が目標を設定し、一定期間内にその目標を達成できるように自発的に行動することを目的としています。また、目標の達成を目指してそれぞれの従業員が努力をすることで個人の成長が見込まれ、その先にある組織全体の成長につながります。
目標管理(MBO)とOKRの違い
目標管理(MBO)と比較される言葉にOKR(Objectives and Key Results)があります。MBOとOKRにはどのような違いがあるのでしょうか。
OKRとは、インテル社やGoogleといったシリコンバレーの企業で多く使われている目標管理手法で、高い頻度で目標の進捗管理と再評価を繰り返し、効率よく目標達成へのプロセスを進めていきます。
OKRは全社で目標を共有するため、従業員のエンゲージメントが高まり、部署間のコミュニケーションが良くなるのがメリットです。一方で、仕組みの導入と定期的な進捗評価に時間がかかるというデメリットも存在します。
MBOとOKRの違いには以下のようなものがあります。
- MBOは100%達成を目的とし、OKRは60~70%達成の大きな目標設定をする。
- MBOは人事評価に連動しているが、OKRは連動していない。
- MBOは1年間で評価するが、OKRは1~3か月で再評価を繰り返す。
- MBOは本人と上司間で共有され、OKRは全社で共有される。
それぞれのメリットとデメリットを把握した上で、取り組むことが重要です。
目標管理(MBO)が広まった背景
日本企業は古くから年功序列の組織制度で運用されてきました。右肩上がりで経済が順調に発展している間は年功序列でも会社の運営は問題がありませんでしたが、時代の変化を背景に年長者のコストや個々の成果に給与が必ずしも対応していないことが会社の課題になってきました。そこで、従業員の能力と成果によって人事評価をする動きが生まれ、目標管理(MBO)が広まりました。
目標管理制度を導入することで、年功序列によるコストや評価に対する不満を改善することができ、成果に沿った人事評価ができるようになりました。目標管理が組織の業績に直結したことで、取り入れる企業が増えてきた背景があります。
多くの組織でジョブ型成果主義人事制度と目標管理制度の導入・定着を手掛けてきたプロフェッショナルのコンサルタントが、目標管理制度の基本的な考え方から効果の出る実践的運用方法までを、わかりやすく解説しています。
既に目標管理制度を導入している企業はもちろん、これから目標管理制度の導入を検討している企業に役立つ内容ですので、是非ご活用ください。
⇒「目標管理制度の基本的な考え方から効果の出る実践的運用方法の解説資料」を無料でダウンロード
目標管理(MBO)のメリット
目標管理(MBO)を導入することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 従業員のモチベーションアップ
- 納得感のある評価ができるようになる
- 目標に対しての振り返りができる
- 従業員の自立心を高める
それぞれのメリットについて解説します。
従業員のモチベーションアップ
目標管理(MBO)を導入すると、従業員は目標の達成に向けて、やるべきことが明確になり能動的に仕事に取り組む必要が生じるため、働きがいが生まれます。また、自分の目標の会社における位置づけを理解することで、自分の仕事が組織の成果につながることを実感できるでしょう。このように目標管理(MBO)は従業員に対して動機付けの役割を果たし、従業員の仕事に対するモチベーションの向上が期待できます。
納得感のある評価ができるようになる
従業員は目標管理(MBO)で設定した目標の達成度合いによって定量的に評価されるため、納得感のある評価ができるようになります。目標は個々によって異なりますが、内容は上司と相談してお互いの合意のもとで決められるため、公平な評価が実現できます。
なお、目標管理(MBO)の目標設定には上司の能力も重要です。あまりにも高い目標だと従業員はやる気を失い、逆に低すぎる目標だとモチベーションアップにつながらないことがあるためです。従業員の能力に合った適切な目標を設定することでMBOの効果を最大限発揮できるようになります。
目標に対しての振り返りができる
目標に対して振り返りができる点も目標管理(MBO)導入のメリットです。自分の成果が定量的に測定できるため、何ができていて何が足りていないかなど目標達成に向けての自分の課題が明確になります。
上司は部下と共にプロセスの振り返りをして、部下にフィードバックをしてあげるとよいでしょう。取り組むべき課題を明確にしたり軌道修正したりすることで目標の達成が促進されます。
従業員の自立心を高める
目標管理(MBO)の導入は、従業員の自立心を高める効果があります。上司からの指示を待つ従業員ではなく、目標達成に向けて自分で考えて工夫した取り組みをするようになります。従業員の自立心が高まると仕事を通してスキルアップしやすくなり、個人の成長を促します。
目標管理(MBO)を導入する際のよくある課題
目標管理(MBO)を導入する際には、どのような課題があるのでしょうか。導入時に発生しやすい課題について、解説します。
達成しやすい低い目標を設定してしまう
目標管理(MBO)で立てた目標の達成度が人事評価に影響するため、従業員は低い目標の方が評価されやすいと考え、達成しやすい低い目標を設定してしまう点が目標管理(MBO)の課題として挙げられます。
達成しやすい低い目標を設定させないためには、上司が目標の難易度を把握しておくことが必要です。面談を通して目標の難易度についてよく話し合い、従業員のレベルに合わせた目標を設定をしましょう。
マネジメント工数がかかる
目標管理(MBO)導入時は、部下との面談回数が多くなります。目標設定時や、目標の進捗確認、定期的な評価制度などマネジメント工数が増えることは目標管理(MBO)のデメリットと言えます。
目標管理(MBO)を継続的に実施することによって、上司のマネジメントスキルの向上が期待できます。さらに目標管理(MBO)が社内に浸透すると、目標管理にかけたマネジメント工数が企業の成長のための投資コストとして活きるようになります。
MBOに関係していない業務をしなくなる
目標管理(MBO)導入時は目標への意識が高まっているため、MBOに関係していない業務には消極的になったり取り組まなくなってしまったりする場合があります。MBOに関係していない業務も会社にとっては不可欠な仕事であるため、このような事態は避けるべきです。そのため、業務全体をカバーできる目標を設定することで、関係していない業務がなくなり、MBOと無関係な業務をしなくなるという課題を改善できます。
多くの組織でジョブ型成果主義人事制度と目標管理制度の導入・定着を手掛けてきたプロフェッショナルのコンサルタントが、目標管理制度の基本的な考え方から効果の出る実践的運用方法までを、わかりやすく解説しています。
既に目標管理制度を導入している企業はもちろん、これから目標管理制度の導入を検討している企業に役立つ内容ですので、是非ご活用ください。
⇒「目標管理制度の基本的な考え方から効果の出る実践的運用方法の解説資料」を無料でダウンロード
目標管理(MBO)を導入する流れ
目標管理(MBO)を導入するには、以下のような流れで進めます。
- Step1:各職務の成果責任の作成
- Step2:目標のKPIの設定
- Step3:社内説明会と目標設定の練習セッション
- Step4:本格運用
それぞれのStepについて解説します。
Step1:各職務の成果責任の作成
目標管理(MBO)の導入の前段階として、会社のビジョンや中期計画などに基づいて、「成果責任」を作ります。「成果責任」とは、例えば「法人営業部長」や「経理部長」などの各職務において、会社に対してどのような責任を負うのかを言葉で表したものです。これを明確化し、それぞれの職務がその責任を全うすることで、会社の経営目標が達成できるようにします。「成果責任」を明確化したうえで、それに基づき年度ごとの目標設定を行うことで、会社の経営目標達成に結び付く目標設定を行うことができます。
Step2:目標のKPIの設定
Step1で明確化した「成果責任」の全う度合いをどの様な指標(KPI:Key Performance Indicator)で測るのかを設定します。これは年度毎に設定する目標の達成度合いを測る指標にもなります。最もわかりやすい例は、売上や利益などの定量的な指標です。ただし、KPIは定量指標だけではありません。例えば、「法人事業部の戦略の策定」の項目での業績指標は「戦略の質」という者になります。そしてそれを評価する場合には、「戦略の質」の内容をあらかじめ明確にしておきます。
Step3:社内説明会と目標設定の練習セッション
導入にあたっては、目標管理(MBO)を導入する目的、基本的な考え方などを丁寧に説明し、社員が納得の上で積極的に取り組んでもらう必要があります。特に導入の目的や狙いについては社長自ら社員に語り掛けることも重要です。
そのうえで、いきなり本格運用を始めるのではなく、目標設定から評価までの一連の流れを実際に練習セッションとしてやってみることも有効です。例えば事業年度が4月から始まる会社であれば、その前の1月頃に、3月末までの事業年度の目標と大まかな着地込みを想定して評価までやってみるのが良いでしょう。
Step4:本格運用
そして新しい年度からいよいよ本格運用を始めます。まずは年初に目標設定から始めます。最初は慣れない点が多いと思いますので、目標管理に精通した人事担当者や外部のコンサルタントなどが介入しながら、正しい目標設定のやり方を習得していくのが一般的です。
目標設定が正しくできると、その後の運用は非常にスムーズに回るようになります。導入初年度は根気よく、正しいやり方を社内に浸透させていくのが重要です。
多くの組織でジョブ型成果主義人事制度と目標管理制度の導入・定着を手掛けてきたプロフェッショナルのコンサルタントが、目標管理制度の基本的な考え方から効果の出る実践的運用方法までを、わかりやすく解説しています。
既に目標管理制度を導入している企業はもちろん、これから目標管理制度の導入を検討している企業に役立つ内容ですので、是非ご活用ください。
⇒「目標管理制度の基本的な考え方から効果の出る実践的運用方法の解説資料」を無料でダウンロード
目標管理(MBO)を運用する際のポイント
目標管理(MBO)を運用する際には、以下のようなポイントがあります。
- 従業員の自主性を尊重する
- 定量だけでなく定性面での目標も立てる
- 従業員の能力を引き出すような目標を立てる
- 抽象的ではなく具体的な目標を立てる
- 管理職に任せきりにならない
それぞれのポイントについて解説します。
従業員の自主性を尊重する
目標管理(MBO)には、従業員の自立心を促す目的もあります。従業員の目標を上司が一方的に決めないようにしましょう。話し合う場面は重要ですが、あくまでも従業員が自分で決めた目標を尊重してあげるようにします。従業員の自主性を尊重してあげることから成長につながります。
定量だけでなく定性面での目標も立てる
目標管理(MBO)では定量的な目標ばかりを立てがちですが、定性的な目標設定も立てるようにしましょう。定性的な目標は「目指すべき理想の状態」を指します。例としては、顧客満足度を高めて既存顧客からリピート受注をもらう、週に1回チームに知見を共有して社内で信頼を得るなどが挙げられます。定量面だけでなく、定性面での目標も立てて幅広い目標設定となるように調整しましょう。
従業員の能力を引き出すような目標を立てる
目標管理(MBO)では、従業員の能力を引き出すような目標を立てましょう。苦手を克服することばかりに目が行くと、強みが失われてしまうことがあります。仕事の成果は主に個々の強みからもたらされるものです。現在の自分の能力レベルを正しく把握し、目標が達成できたときにスキルアップが実現できているイメージを描けることが大切です。
抽象的ではなく具体的な目標を立てる
抽象的ではなく、具体的な目標を立てることが目標管理(MBO)では重要です。目標に具体性を持たせるためには、立てた目標と行動を切り分けて設定してあげるといいでしょう。
例えば、営業成績の10%アップという目標を立てたのならば、〇〇の商品に特化して訪問回数を月に10件増やす、といった行動計画をセットにして設定します。
管理職に任せきりにならない
目標管理(MBO)は上司の役割が重要ですが、管理職に任せきりにならないことが大切です。上司の評価だけで個人の評価が確定してしまわないよう、会社として従業員の評価を客観的に見る必要があります。評価に偏りが生まれるのを防ぐために、管理職向けのガイドラインの作成や研修をおこなうと良いでしょう。
また、他部署の好事例を共有するのもおすすめです。次年度の目標設定において精度が高まり、組織全体でマネジメントスキルの向上が図れます。
多くの組織でジョブ型成果主義人事制度と目標管理制度の導入・定着を手掛けてきたプロフェッショナルのコンサルタントが、目標管理制度の基本的な考え方から効果の出る実践的運用方法までを、わかりやすく解説しています。
既に目標管理制度を導入している企業はもちろん、これから目標管理制度の導入を検討している企業に役立つ内容ですので、是非ご活用ください。
⇒「目標管理制度の基本的な考え方から効果の出る実践的運用方法の解説資料」を無料でダウンロード
まとめ
目標管理制度(MBO)を利用するメリットや導入する流れ、導入するポイントについて解説をしてきました。目標管理(MBO)は従業員の成長を促し、面談を通して上司のスキルアップも期待できます。MBOが浸透することで、組織全体の成長にもつながるメリットもあります。
目標管理(MBO)の効果をよく理解し、毎年制度の見直しを続けて企業に合ったより良い制度に育てていきましょう。
組織・人事プロフェッショナル養成講座を配信中!
人事制度を学んだことがない方向けに、企業における人事の役割を体系的に学べる講座をオンデマンド型で配信しております。
- 全10回の講座でどこよりも「深く」「幅広く」学べる
- 合計約900ページにも及ぶ資料をプレゼント
- オンラインでいつでもどこでも受講可能!
- 講師への質問が可能!
本講座では、人事に配属されたばかりの新人の方はもちろん、今の人事のやり方が正しいか今一つ自信が持てない経営者、人事責任者、人事コンサルタントを対象に、企業における人事精度を一から学ぶことができます。
記事監修

- 前田 正彦(まえだ まさひこ)
- 株式会社スキルアカデミー 代表取締役CEO
慶應義塾大学経済学部卒業。米国マサチューセッツ工科大学経営大学院(Sloan School of Management)修了。株式会社前田・アンド・アソシエイツ代表取締役(現職)。
株式会社NTTデータにて金融システムの開発に携わった後、 数々のコンサルティングファームにて、戦略立案から実行・定着までのプロジェクトを数多くリードしてきた。
その後人事・組織コンサルティングの必要性を痛感し、当該分野のプロジェクトを立ち上げ、戦略から人事・組織コンサルティングまで一貫したサービスを提供している。
スキルアカデミーにおいては、代表取締役CEOとしてAI人事4.0事業全体の推進をリードするほか、組織・人事・人材開発などの案件を数多くリードしている。
また組織診断・管理特性、職務等級制度・成果報酬制度などツールを開発。グローバル人事プロフェッショナル組織であるSHRM認定資格を取得。