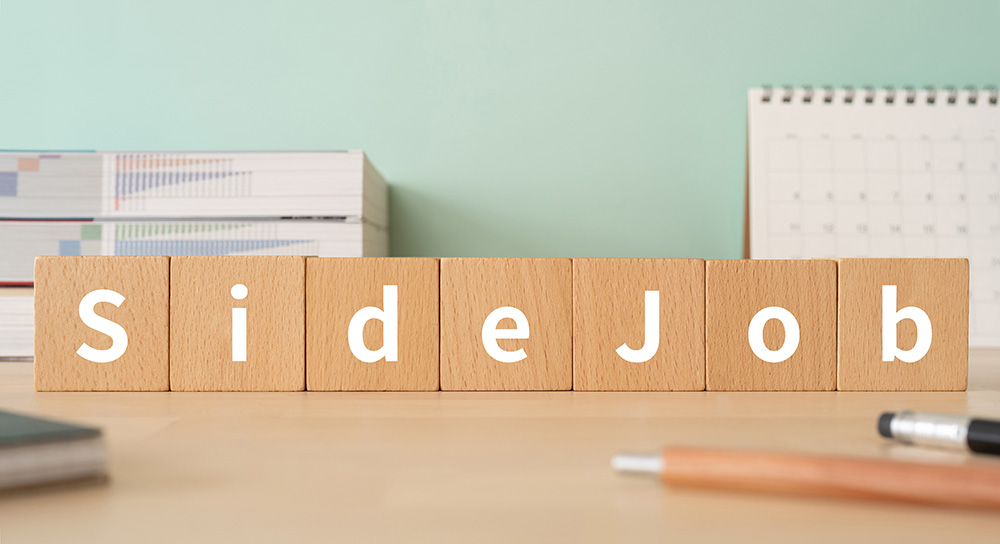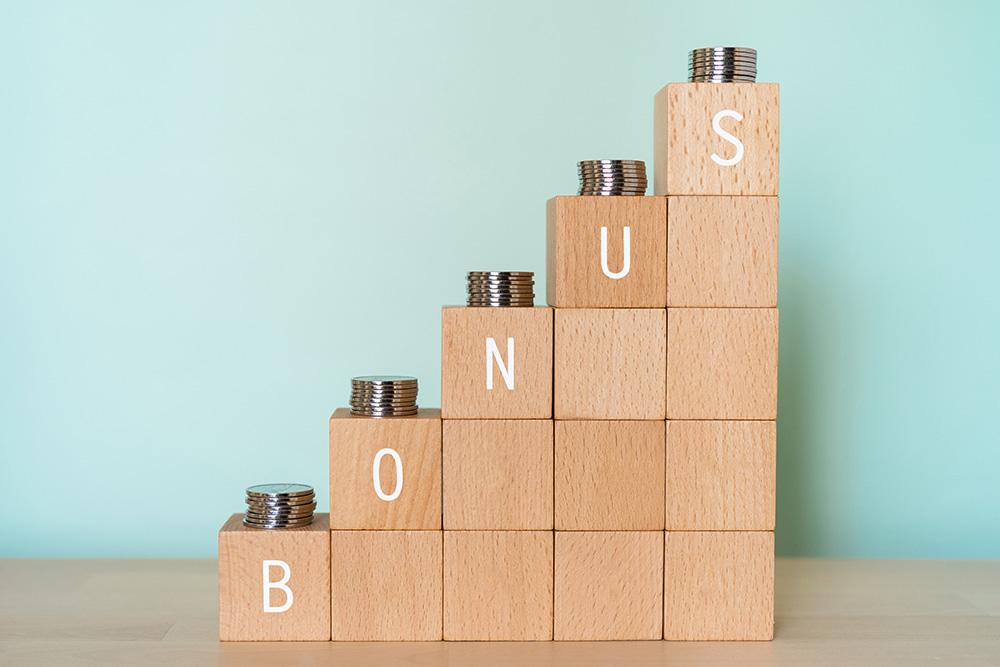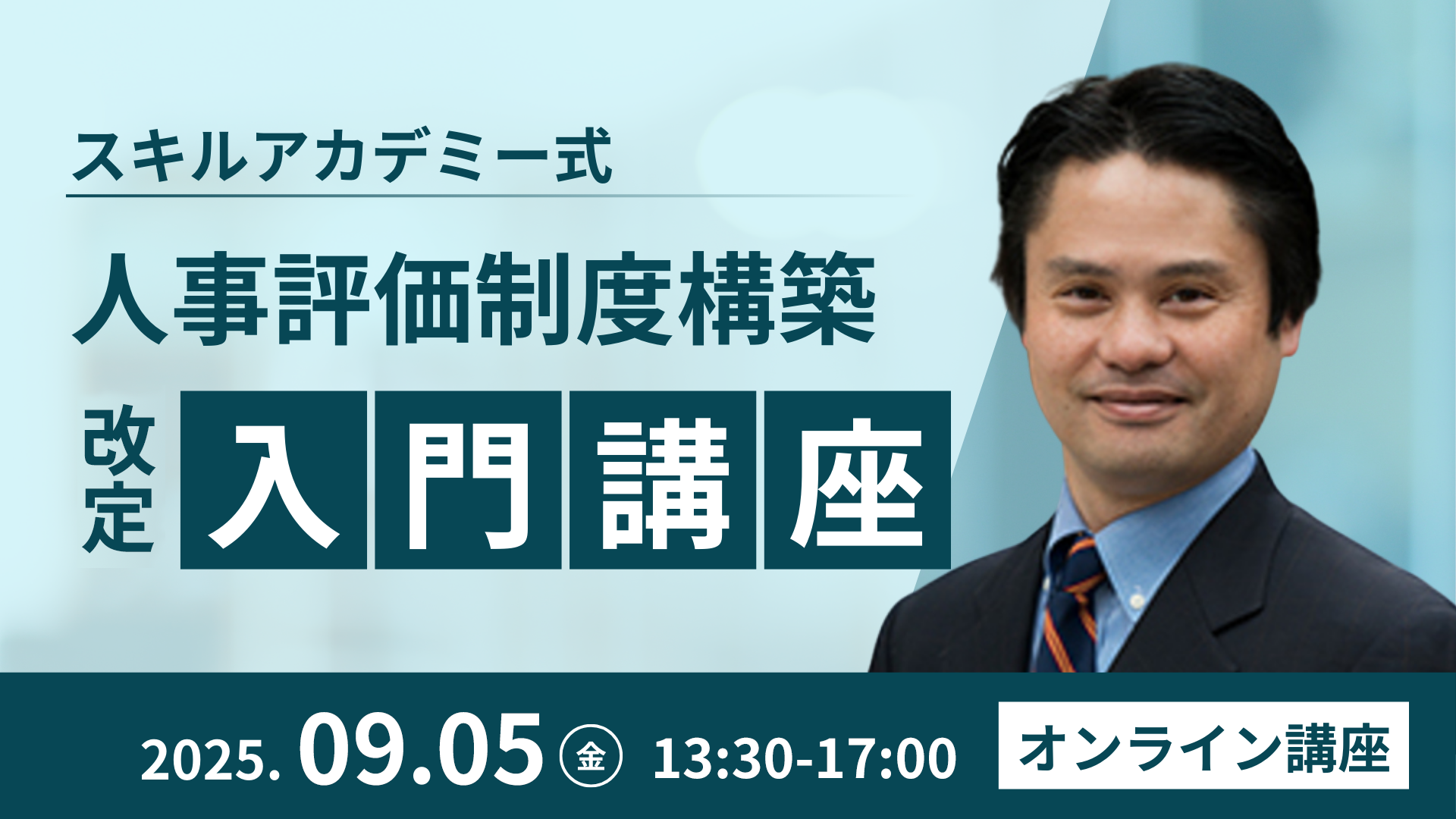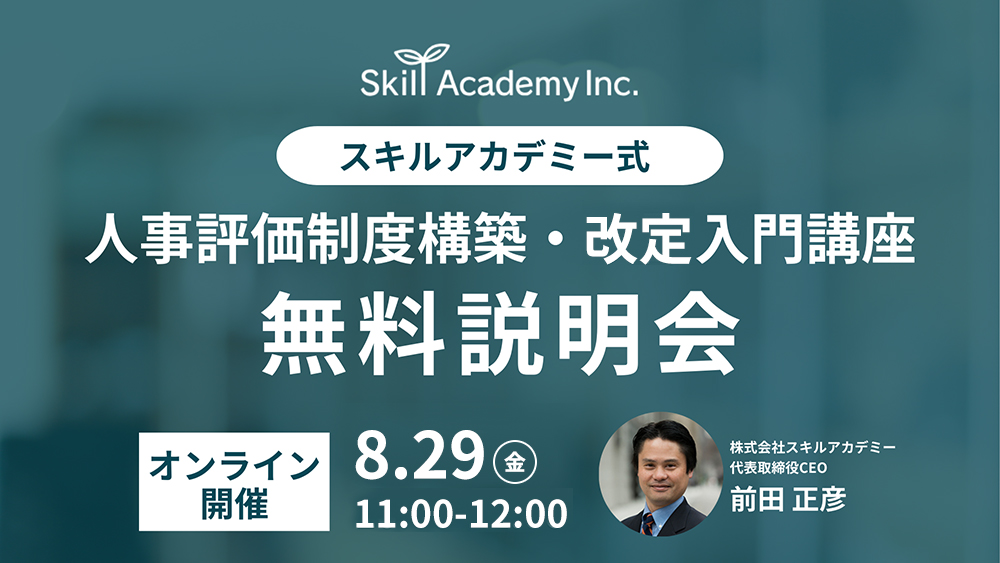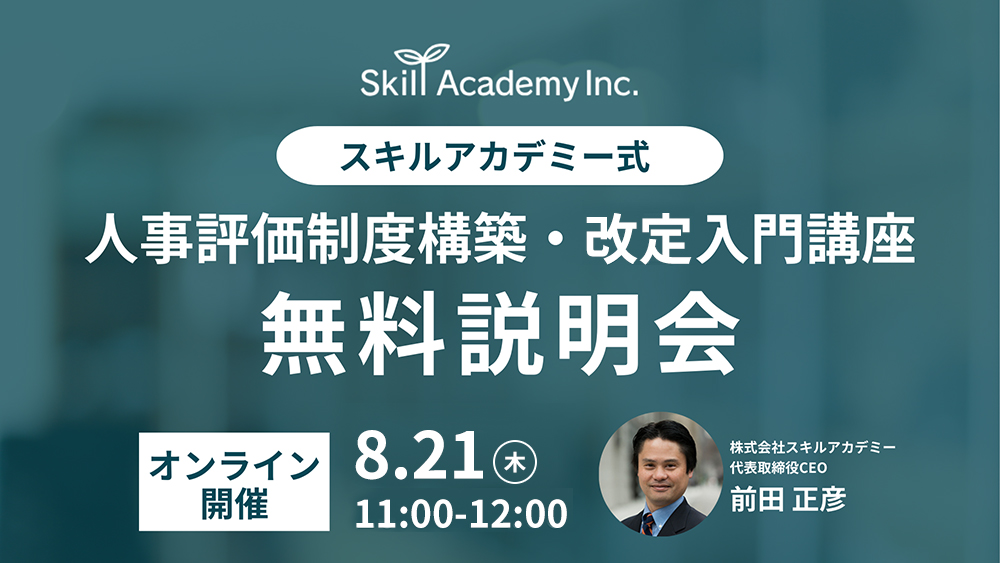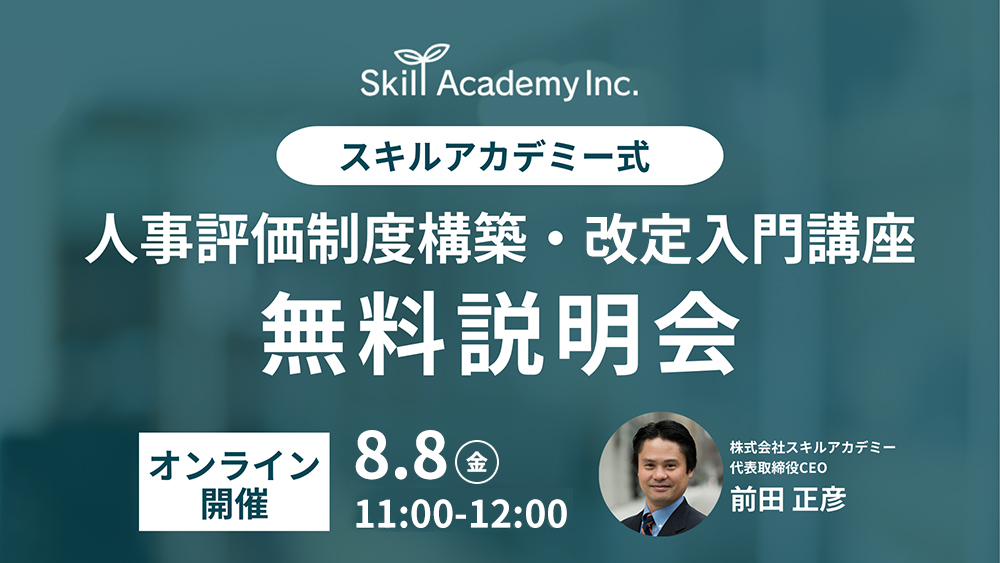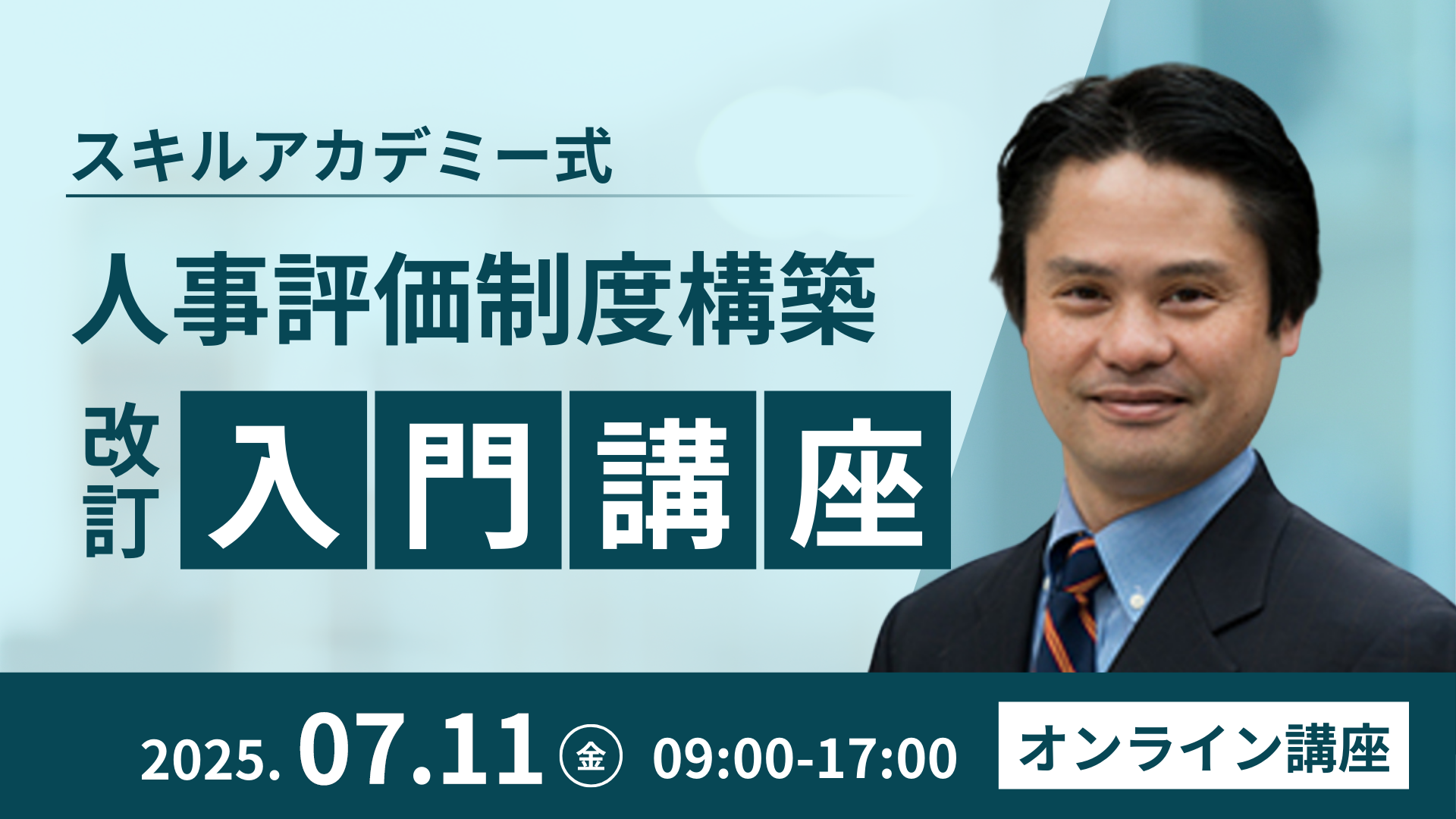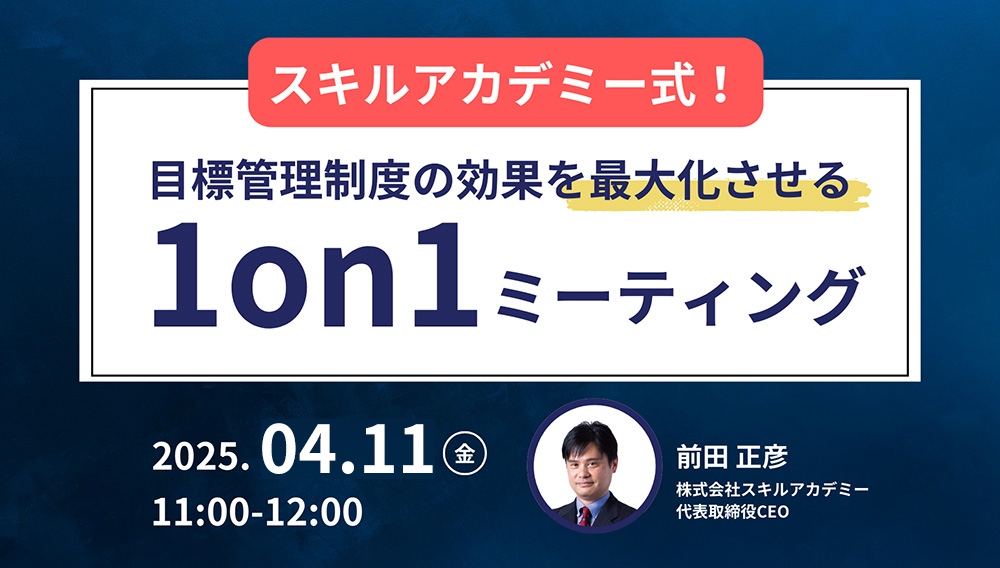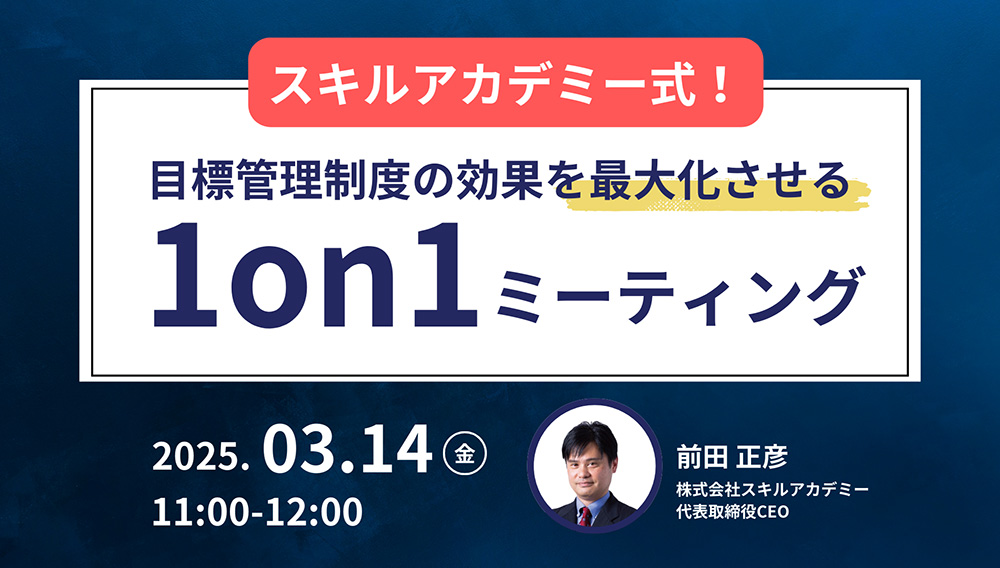人事コンテンツ
研修後アンケートの実施意義とは|設問例や設計時のポイントも解説
2025/3/17
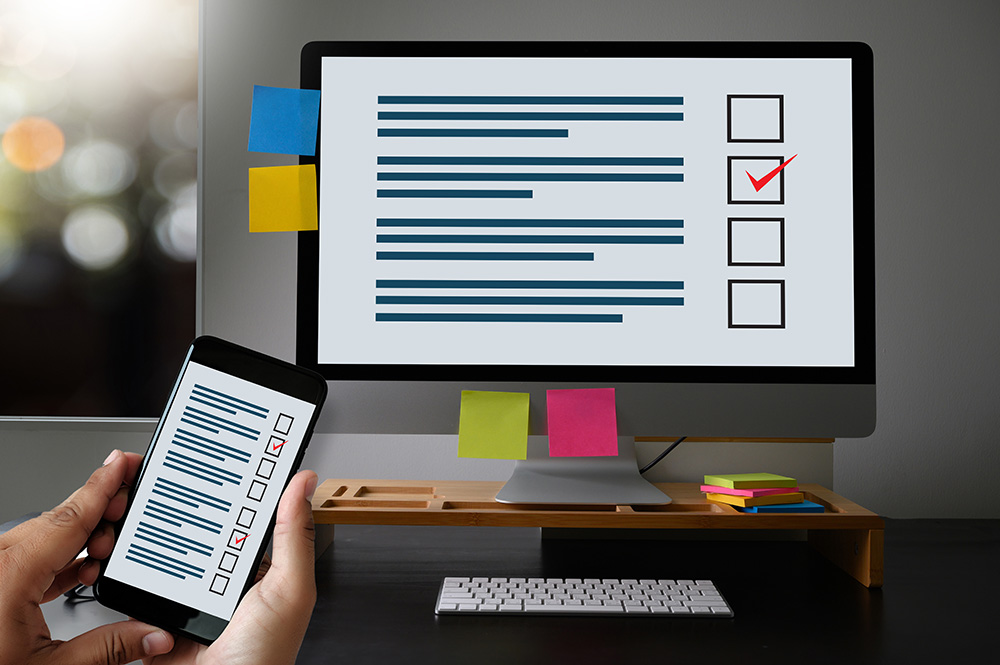
- 研修後にアンケートを実施する意義とは
- 研修後のアンケートを設計する際のポイント
- 研修後アンケートの設問例
- 研修後のアンケートだけでは効果測定には限界がある
- 効果的な研修を実施するなら設計がポイント
- まとめ
「研修後のアンケートを実施すべきだろうか」「アンケート結果をどのように活用すべきかわからない」といった課題を抱える企業も多いのではないでしょうか。
研修後のアンケートを実施しなければ、研修の効果測定が不十分となり、社員の学習状況を正確に把握できない可能性があります。その結果、研修の効果が最大化されず、社員の成長や組織の発展に悪影響を及ぼす恐れがあるでしょう。
本記事では、研修後にアンケートを実施する意義や、アンケートから得られる情報、そしてアンケート結果を効果的に活用するための方法について詳しく解説します。
企業の人材育成担当者の方々にとって参考になる内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。
研修後にアンケートを実施する意義とは
研修後にアンケートを実施することには、主に以下2点の意義があります。
- 研修の反応を把握できる
- 研修の改善点の参考にできる
これらの意義を理解し適切に活用することで、研修の効果を最大化し、組織の成長へとつなげられます。
研修の反応を把握できる
研修直後にアンケートを実施することで、参加者の生の反応を把握できます。
参加者の声は、研修の効果を評価する上で重要な役目を果たします。
具体的には、研修をおこなった時点での社員の反応を観測することで、参加者がきちんと内容を聞いていたか、研修に対してどのような感想を持っているか、などを把握することが可能です。
参加者の反応を細かく分析することで、研修のどの部分が効果的だったか、どの部分に改善の余地があるかを特定でき、研修の改善につなげられるでしょう。
研修の改善点の参考にできる
研修後のアンケートは、研修の改善点を特定する上での貴重な情報源となります。
受講者からのフィードバックを通じて、研修のどの部分に不満や課題があるのかを把握できるためです。
たとえば、内容の難易度、講師の説明のわかりやすさなどに問題はないかを質問し、自由記述で回答してもらうことで、具体的な改善ポイントが判明するでしょう。
もちろん、アンケート結果だけですべての改善点を把握できるわけではありません。長期的な効果や実際の業務への適用状況を評価するには、ほかの調査方法と組み合わせて分析する必要があります。しかし、アンケートは受講直後の反応を収集できる点で有用です。
アンケートで得られた情報を参考にすることで、次回の研修をより効果的に設計し、参加者のニーズにより適した内容にブラッシュアップしていけます。
たとえば、連続しておこなわれる研修の場合、前回の研修アンケート結果を次回の研修に反映させることで、次回の研修からその改善点を反映した研修を実施できるようになるでしょう。
このように、研修後のアンケートは単なる形式的な作業ではなく、研修の質を向上させ、参加者の学習効果を最大化する上での重要なツールとなります。
研修後のアンケートを設計する際のポイント
研修後のアンケートを効果的に設計するためには、以下2つのポイントが重要です。
- 定量的に観測できる項目を設計する
- アンケート項目は多くなりすぎないように設計する
これらのポイントを押さえることで、より有用な情報を収集し、研修の改善に活かせます。
定量的に観測できる項目を設計する
効果的なアンケートを設計する上では、定量的に観測できる項目を含めることが重要です。
定性的な項目のみでは、データの集計や分析が困難となる可能性があります。また、定量的な項目を設けることで、研修の効果や参加者の反応を数値化し、客観的に評価できるでしょう。
たとえば、「講師の説明のわかりやすさ」や「研修内容を実務へ活かせそうか」などの項目を5段階で評価してもらうことで、研修の満足度や理解度、実用性を具体的な数値として把握できます。定量的なデータは、研修の改善点を特定したり、異なる研修間で比較したりする際にも有用です。
また、選択式の質問を設けることも効果的です。「はい」「いいえ」の二択や、複数の選択肢から当てはまるものを選ぶ形式の質問を用意することで、受講者が回答しやすく、分析も容易になるでしょう。
ただし、定量的な項目だけでなく、自由記述欄を設けることもポイントです。「具体的にどのような点が良くて、どの点に改善が必要なのか」など、数値では表現しきれない具体的な意見を収集することも忘れないようにしましょう。定量的データと定性的データをバランスよく組み合わせることで、研修の評価をより効果的におこなえます。
アンケート項目は多くなりすぎないように設計する
効果的なアンケートを設計する際の重要なポイントの一つは、アンケート項目を適切な数に抑えることです。項目が多すぎると、回答者の負担が大きくなり、アンケートの質と有効性が低下する可能性があります。
回答に時間がかかりすぎるアンケートでは、研修後の受講者が回答に疲れてしまい、後半の質問に対して適当な回答をしてしまうリスクがあります。その場合、収集したデータの信頼性が損なわれます。
設問例は後述しますが、項目を絞り込む際は以下のポイントを考慮しましょう。
そのため、理想的なアンケートの長さは、回答時間が5〜10分程度で完了できるものであり、項目数は10〜20項目程度に抑えることが好ましいです。
- 研修の主要な目的に直接関連する項目を優先する
- 重複する内容の質問を避ける
- 研修改善につながる質問を選ぶ
適切な量・項目のアンケートを設計することで、回答者の負担を軽減し、より正確で有用な情報を収集可能です。
重要な項目はアンケート上部に記載する
効果的なアンケートを設計する上では、重要な質問項目をアンケートの上部に配置することも意識しましょう。
アンケートの回答者は、一般的に最初の部分により多くの注意を払う傾向があります。時間が経つにつれて、または質問が続くにつれて、回答者の集中力や興味が低下する可能性があるため、最も重要な質問を上部に配置することで、より正確で内容の濃い回答を得られる可能性が高まります。
重要な項目を上部に配置する際の具体的な方法としては、以下が挙げられるでしょう。
- 研修の全体的な評価や満足度に関する質問は、最初に配置する
- より具体的または詳細な質問は、それ以降に配置する
たとえば、「この研修は全体としてどの程度役立ちましたか?(選択式)」という質問を最初に置き、次に「この研修で最も有用だった点は何ですか?(自由記述式)」といった質問を配置するといった具合です。
このように質問の順序を工夫することで、アンケート全体の回答率と質を向上させ、より価値のある情報を収集しやすくなります。ただし、アンケート全体のバランスも考慮し、後半の質問も軽視されないよう注意することが大切です。
研修後アンケートの設問例
効果的な研修後アンケートを作成するためには、適切な設問を選択することが重要です。
以下に、よく使用される設問例とその意図をご紹介します。これらの例を参考にしながら、自社の研修目的や内容に合わせてカスタマイズすることがおすすめです。
| 設問 | 回答形式 | 意図 |
|---|---|---|
| 1. 研修前にどんなことに悩んでいましたか? | 自由記述 | 参加者の受講前の状態を把握し、研修がニーズに合っていたかを評価する |
| 2. 研修の内容は、あなたの業務に役立つと思いますか? | 複数選択・自由記述 | 研修の実用性を把握する |
| 3. 研修を受けて、今日からどんな行動をしますか? | 自由記述 | 学んだ内容の実践意欲と具体的な行動計画を確認する |
| 4. 今回の研修を100点満点で評価すると何点ですか? | 数値入力 | 研修の全体的な満足度を定量的に測定する |
| 5. 講師の説明はわかりやすかったですか? | 5段階評価 | 講師のパフォーマンスを評価する |
| 7. 研修で最も印象に残った内容は何ですか? | 自由記述 | 特に効果的だった内容を特定し、今後の研修内容に反映する |
| 8. 研修の改善点や課題があれば教えてください | 自由記述 | 参加者視点からの具体的な改善案を収集する |
| 9. 今後受講したいテーマを教えてください | 複数選択・自由記述 | 今後の研修ニーズを把握し、研修計画に反映させる |
| 10. この研修を同僚にお勧めしたいと思いますか? | 複数選択・理由 | 研修の推奨度を評価する |
これらの設問は、定量的な評価と定性的なフィードバックをバランスよく組み合わせています。また、研修の満足度だけでなく、学習成果や今後の行動変容についても把握できるよう設計されています。
アンケートを設計する際は、自社の研修目的や参加者の属性に合わせて、これらの設問をアレンジするとよいでしょう。また、アンケートの長さにも注意を払い、回答者の負担にならない程度に調整するようにしてみてください。
研修後のアンケートだけでは効果測定には限界がある
研修後のアンケートは、参加者の直接的な反応や理解度を把握する上で有用なツールですが、研修の効果を測定する上では、アンケートだけでは不十分な側面があります。
研修後のアンケートで主に測定できるのは、研修終了時点での参加者の反応、満足度、理解度などです。これらの情報は確かに価値がありますが、研修の本当の目的である「行動変容」や「業績向上」を直接測定することはできません。
たとえば、プレゼンテーション研修を受けた参加者が、研修直後は「非常に有意義だった」と回答したとしても、実際の職場でプレゼンテーションスキルを発揮できているかどうかは、アンケートだけでは把握できません。
真の研修効果を測定するためには、長期的かつ多面的な効果測定をしていきましょう。研修後の行動変容や業績の観察・評価や、360度フィードバックなどさまざまな方法を組み合わせることで、研修の長期的な効果や実際の業務への影響を、より正確に把握することができます。
たとえば、研修から数か月後に参加者の上司や同僚からフィードバックを集めたり、研修内容に関連する業績指標の推移を分析したりすることで、研修内容が実際の業務にどのように活かされているかを確認できるでしょう。
アンケートは効果測定の重要な一部ではありますが、それだけで研修の効果を測定するには情報が不十分であることに留意しなければなりません。
効果的な研修を実施するなら設計がポイント
効果的な研修を実施し、その効果を正確に測定するためには、研修の設計が重要です。適切な設計なしにおこなわれた研修は、たとえ参加者の満足度が高くても、実際の業務パフォーマンス向上につながらない可能性があります。
効果的な研修設計のポイントは、明確な目標・目的を設定することです。
どのような能力を、どの程度向上させたいのか、そしてその能力向上がどのように組織の目標達成につながるのかを明確にする必要があります。この部分が曖昧であると、研修内容が的外れなものになってしまい、どれだけ研修を実施しても、人材育成も組織の成長も実現しないリスクがあるでしょう。
次に、設定した目標を達成するために最適な研修内容と方法を検討します。講義、ワークショップ、オンライン学習など、学習目標に最も適した方法を選ぶことが重要です。
能力は、大きく「知識」「スキル」「コンピテンシー」の3つに大別されますが、それぞれ以下の研修方法が適しています。
- 知識:座学
- スキル:実践型(ロールプレイングなど)の研修、OJT
- コンピテンシー:研修+長期間の実地での実践・フィードバック
知識はインプットがメインであるため座学が向いており、スキルとコンピテンシーは座学でのインプットだけでなくアウトプットも必要です。とくに、コンピテンシーは行動特性に関わる能力のため、研修だけで完結させるのは難しく、長期間にわたって現場で訓練をしていく必要があります。
このように、研修の設計段階から効果測定まで一貫した計画を立てることで、研修の有効性を最大化できるでしょう。
まとめ
研修後のアンケートは、参加者の直接的な反応や理解度を把握する上で有用ですが、長期的な行動変容や業績向上を測定するには限界があります。そのため、アンケート以外の方法も組み合わせた多面的なアプローチが必要です。
また、効果的な研修を実施するには、設計も重要です。明確な目標設定や適切な研修内容の選択、そしてフォローアップもしっかりと計画するようにしましょう。それにより、「研修のための研修」ではなく、実際の業務改善や組織目標の達成に直結する効果的な研修を実施できるようになります。
綿密な研修設計と包括的な効果測定を通じて、研修の有効性を最大化し、組織の成長を加速させていきましょう。
組織・人事プロフェッショナル養成講座を配信中!
人事制度を学んだことがない方向けに、企業における人事の役割を体系的に学べる講座をオンデマンド型で配信しております。
- 全10回の講座でどこよりも「深く」「幅広く」学べる
- 合計約900ページにも及ぶ資料をプレゼント
- オンラインでいつでもどこでも受講可能!
- 講師への質問が可能!
本講座では、人事に配属されたばかりの新人の方はもちろん、今の人事のやり方が正しいか今一つ自信が持てない経営者、人事責任者、人事コンサルタントを対象に、企業における人事精度を一から学ぶことができます。
記事監修

- 前田 正彦(まえだ まさひこ)
- 株式会社スキルアカデミー 代表取締役CEO
慶應義塾大学経済学部卒業。米国マサチューセッツ工科大学経営大学院(Sloan School of Management)修了。株式会社前田・アンド・アソシエイツ代表取締役(現職)。
株式会社NTTデータにて金融システムの開発に携わった後、 数々のコンサルティングファームにて、戦略立案から実行・定着までのプロジェクトを数多くリードしてきた。
その後人事・組織コンサルティングの必要性を痛感し、当該分野のプロジェクトを立ち上げ、戦略から人事・組織コンサルティングまで一貫したサービスを提供している。
スキルアカデミーにおいては、代表取締役CEOとしてAI人事4.0事業全体の推進をリードするほか、組織・人事・人材開発などの案件を数多くリードしている。
また組織診断・管理特性、職務等級制度・成果報酬制度などツールを開発。グローバル人事プロフェッショナル組織であるSHRM認定資格を取得。