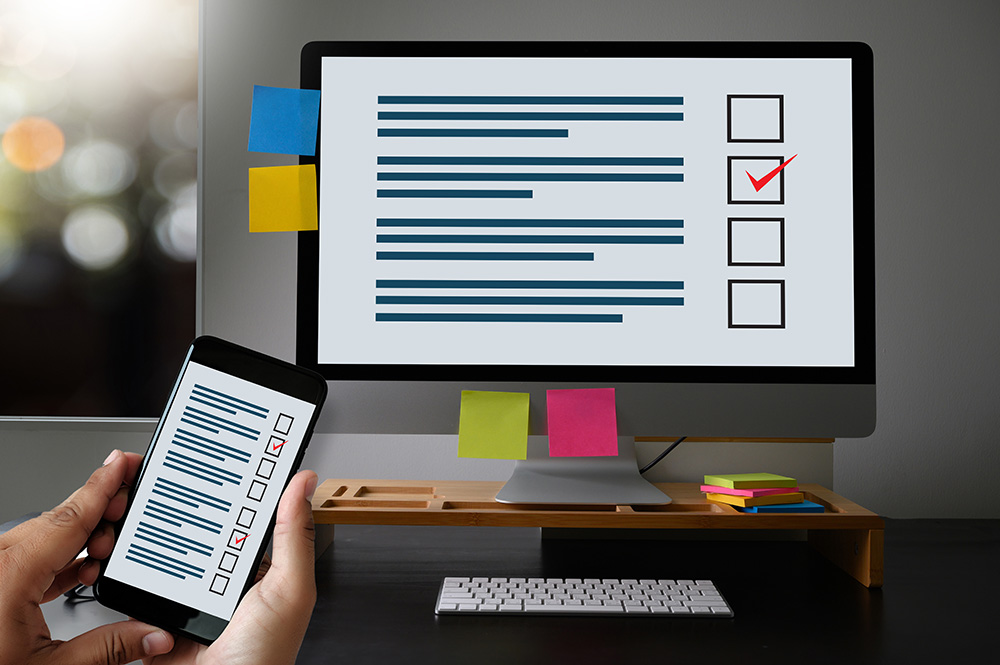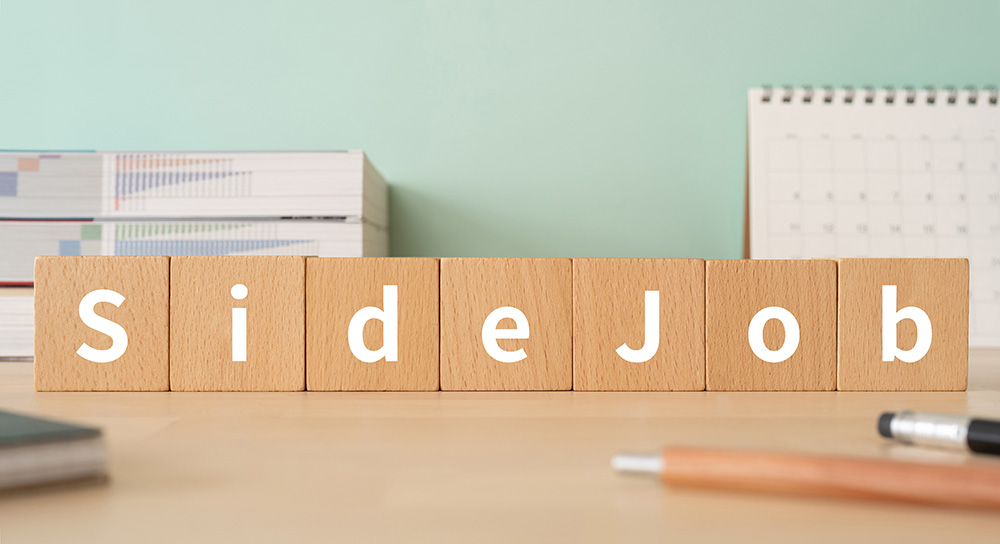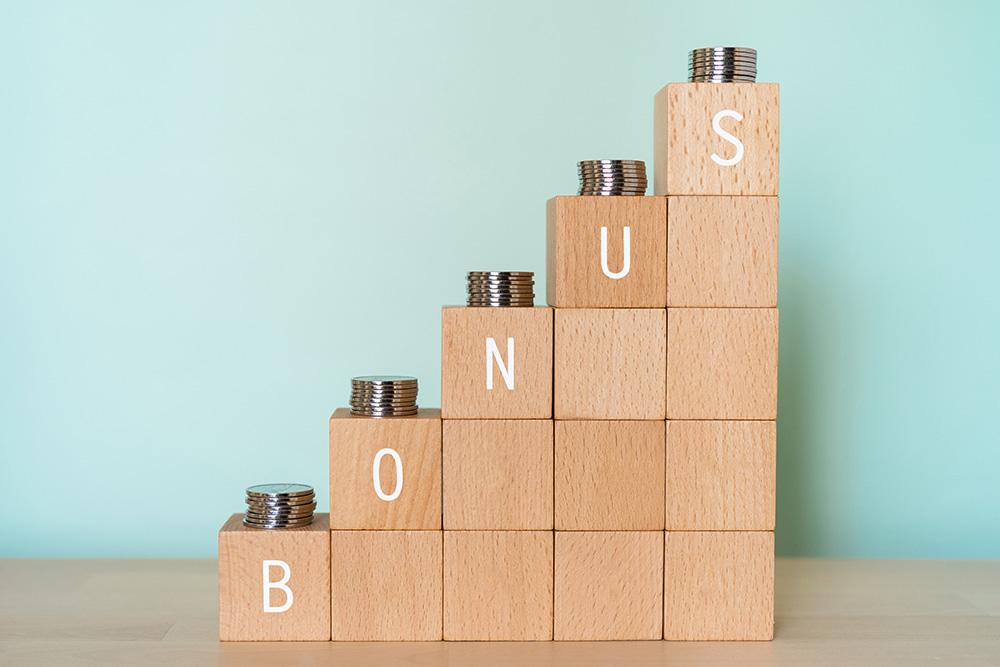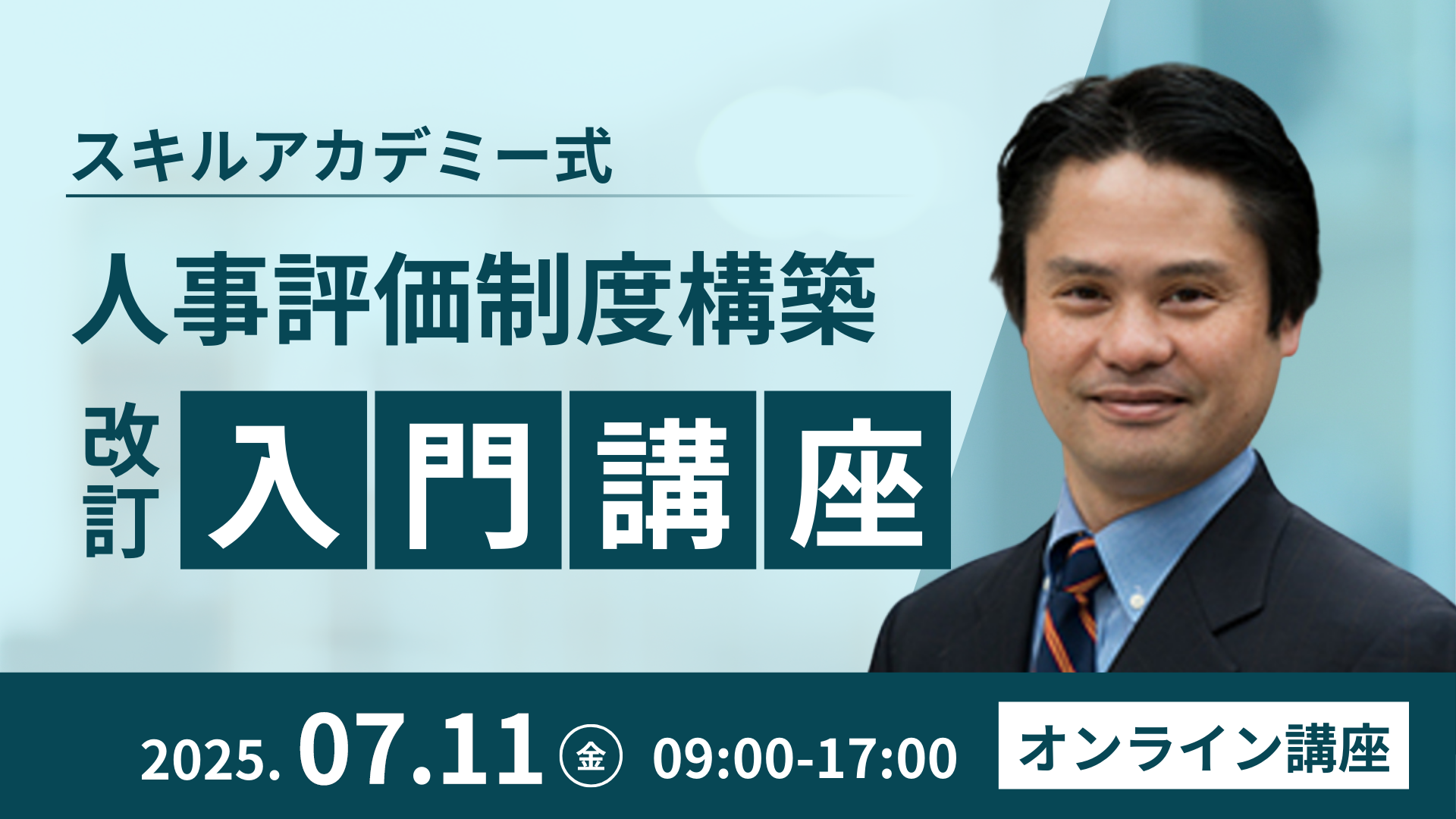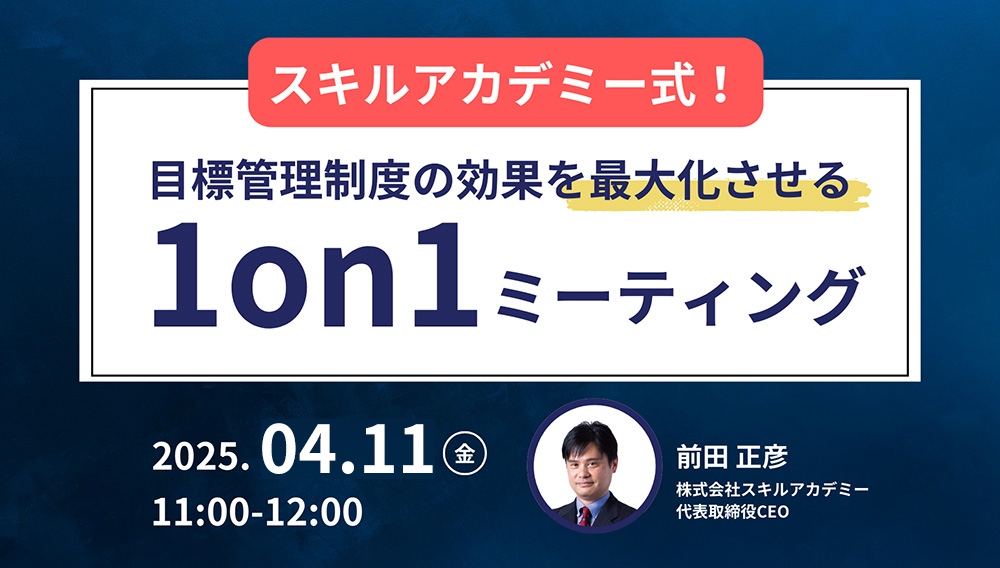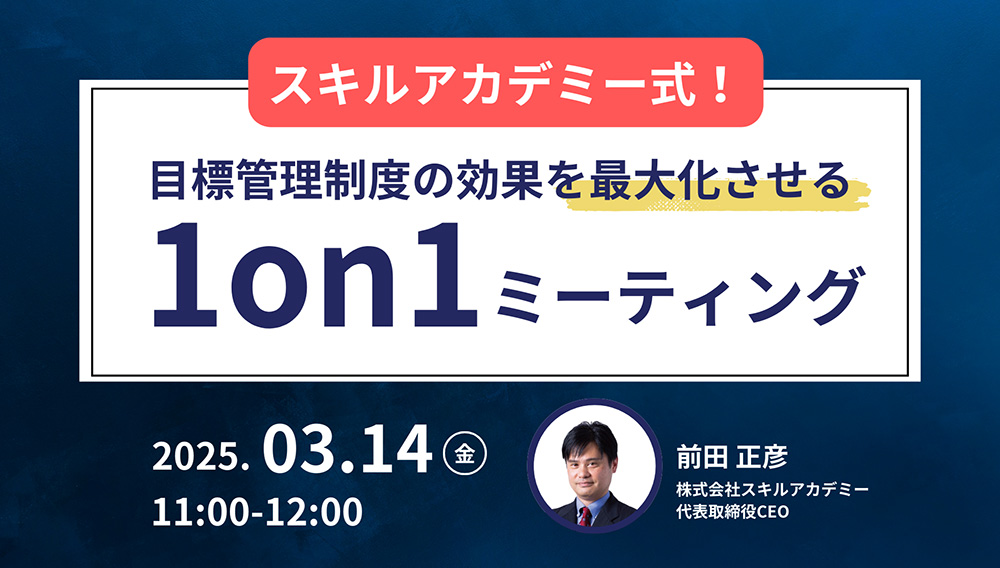人事コンテンツ
研修を内製化するメリット・デメリット手順についても詳しく解説!
2025/3/17

「従業員の増加に伴い、効果的な人材育成が急務となっている」「外注の研修では十分な効果が得られず、内製化を検討せざるを得ない」と悩む人事責任者の方は多いのではないでしょうか。
研修を内製化しようと思っても、本当に内製化すべきなのか、どのようにして進めるべきなのか、判断するのは難しいですよね。
そこで本記事では、研修内製化のメリットとデメリット、内製化に適した企業の特徴、そして効果的な導入方法について詳しく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、今後の参考としてください。
研修を内製化するメリット
自社で研修を設計・実施することで得られる利点は、決して少なくありません。
研修の内製化で得られる主なメリットとしては、以下が挙げられます。
- 自社独自の内容を設計できる
- 講師の育成につながる
- 属人化したベテランのノウハウを標準化して浸透させられる
- 外注費用を削減できる
内製化のメリットについて、詳しく見ていきましょう。
自社独自の内容を設計できる
研修を内製化するメリットの1つは、自社の特性に合わせたカスタマイズが可能になることです。
研修を自社で設計することにより、自社が大切にしている独自のノウハウや考え方を研修に盛り込めます。とくに、企業文化の研修など外部に委託しては十分に伝えきれない内容を組み込めることは、大きな利点といえるでしょう。
たとえば、自社の歴史や成長過程で培われた独自の経営哲学、業界での競争優位性を支える考え方などを、研修プログラムの中心に据えられます。これにより、単なるスキル習得に留まらず、企業のDNAを次世代に継承する場としての機能も果たせるようになります。
また、自社への理解が深まることで、従業員のエンゲージメントが向上し、業務へのモチベーションや定着率向上などのメリットも得られるでしょう。
講師の育成につながる
研修の内製化は、受講者の育成だけでなく、講師を務める社員の成長にもつながります。
講師として研修を担当することは、単に知識を伝えるだけではなく、自身の経験や理解を深める貴重な機会にもなります。研修内容をわかりやすく噛み砕いて伝えていく過程で、講師自身が新たな気づきを得ることも少なくありません。
さらに、講師としての経験は、コミュニケーション能力やプレゼンテーションスキルの向上にもつながります。これらのスキルは、日常の業務や部下の指導においても有用です。
属人化したベテランのノウハウを標準化して浸透させられる
研修を内製化することは、ベテラン社員が長年培ってきた貴重なノウハウを組織全体に浸透させる機会ともなります。
たとえば、業界特有の商習慣や顧客対応のコツ、社内システムの効率的な活用法など、マニュアルには記載されていない実践的なノウハウを、具体的な事例を交えて伝えられるでしょう。こうした生きた知識は、若手社員の成長を加速させ、業務の質を向上させます。
さらに、研修を通じてノウハウを体系的に整理し伝承していくことで、これまで個人に依存していた知識やスキルを標準化することも可能です。標準化されたノウハウは、新人教育の質を高め、業務の効率化やサービスの均一化にも役立ちます。
また、ベテラン社員が退職した際にも、ほかの従業員が代わりを務めやすくなる点も利点です。
外注費用を削減できる
研修の内製化がもたらす重要なメリットの1つに、コスト削減も挙げられます。これまですべて外部に委託していた研修を自社で実施することで、大幅な費用削減が期待できるでしょう。
外部の研修機関や講師に依頼する場合、受講者数や研修回数に応じて費用が発生します。とくに大規模な組織や、定期的に研修を実施する必要がある場合、その費用は無視できない金額になることもあるでしょう。
一方、内製化することで、初期の教材開発や講師育成にはある程度の投資が必要となるものの、長期的には大幅なコスト削減につながります。
また、内製化によって研修を柔軟に実施・調整できるようになる点も利点です。
たとえば、急な人事異動や組織変更に伴い、追加の研修が必要になった場合でも、外部に依頼する場合と比べて迅速かつ低コストで対応できます。さらに、研修内容の微調整や更新が外部委託の場合よりも容易におこなえる点も、メリットです。
ただし、コスト削減を追求するあまり、研修の質が低下しないよう注意しなければなりません。
研修を内製化するデメリット
研修の内製化には多くのメリットがありますが、同時にいくつかのデメリットも存在します。
代表的なデメリットは、以下の2つです。
- 内製化にコストがかかる
- 新たなトピックやトレンドへの対応が難しくなる
これらのデメリットを理解し、適切に対処することで、より効果的な内製化を実現できます。
内製化に伴う主な課題について、詳しく見ていきましょう。
内製化コストがかかる
研修を内製化する際に直面する大きな課題の1つが、内製化のコストです。
研修を1から構築する場合、相当な社内リソースを必要とします。研修内容の設計から始まり、適切な講師の選定と育成、効果測定の仕組みづくりなど、多岐にわたる準備が必要です。
これらの作業には、人事部門を中心として時間と労力が大きく割かれることになるでしょう。とくに、質の高い教材を作成するためには、評価制度に精通した社内の専門家や経験豊富なマネージャーの協力が不可欠です。そうした人材に協力してもらう際には、通常業務への影響も考慮し、微調整する必要もあります。
効果的な研修を実施するためには、適切な設備や環境の整備も重要です。研修用の会議室の確保や、必要に応じてAV機器などの設備投資も検討しなければなりません。
そのため、研修を内製化する上で発生するこれらのコストと、活用可能な社内リソースを慎重に比較検討し、内製化の是非を判断することが重要です。
場合によっては、段階的な内製化や一部の研修のみを内製化するなど、柔軟なアプローチを取ることが大切といえます。
新たなトピックやトレンドがつかみにくくなる
研修を内製化することで、自社の特性に合わせたカスタマイズが可能になる一方、外部の最新情報やトレンドから遠ざかってしまうリスクがあるでしょう。
内製化により、自社独自の内容は充実し、組織の特性に即した研修を提供できるようになります。しかし同時に、外部の視点や最新の情報、トレンドなどの情報が入りにくくなる可能性があるのです。
たとえば人事の分野では、労働法規の変更やダイバーシティ&インクルージョンの推進、働き方改革、コンプライアンスへの対応など、社会的要請に基づき日々新たなトピックが生まれています。これらの情報に適時対応することが必要となりますが、研修が完全に内製化され、外部の情報が入りづらい状態では、キャッチアップしづらくなるでしょう。
また、トレンドとなるこうしたトピックは、全企業に共通する普遍的な内容となるものも多く、自社で内製化する意義が薄くなるのも難点です。
したがって、完全な内製化ではなく、定期的に外部の専門家を招いてセミナーを開催したり、人事担当者が外部の研修会に参加したりするのがよいでしょう。外部との接点を意図的に設ける努力が必要です。
効果的に研修を実施するには外注と内製化の使い分けが重要
研修を効果的に実施するためには、内製化と外注のバランスを適切に取ることが重要です。
前述のとおり、研修には内製化すべきものと、内製化する意義の薄いものが存在します。
この特性を理解し戦略的に使い分けることで、より効果的な研修プログラムを構築できるでしょう。
すべての研修を内製化しようとすると、主に以下2つの問題に直面します。
- 外部の最新情報やトレンドが入りにくくなる
- 運用コストが増大する
そこで、内製化の意義が薄い研修に関しては、積極的に外注を活用し、内製化と外注を賢く使い分けていく必要があります。たとえば、コンプライアンスや一般的なコミュニケーションスキルなど業界横断的な普遍的内容については、外部に委託するほうが効率的でしょう。
また、自社のノウハウでは対応しきれない専門性の高い領域も同様に、外部に依頼をするのがおすすめです。
たとえば、人事評価制度の構築や研修などは人事制度に関する専門的な知見が必要ですが、そうした領域において、自社で質の高い研修を設計したり、制度改修までしたりするのは困難です。
そのため、内製化する意義の薄いものだけでなく、内製化が難しい分野も、積極的にアウトソーシングをするとよいでしょう。
研修を内製化すべきでないケース
研修の内製化には多くのメリットがありますが、すべての組織や状況に適しているわけではありません。具体的には、以下のような状態の企業では内製化を避けたほうがよいでしょう。
- 研修を内製化する目的が不明瞭なケース
- コストカットだけを目的として研修を内製化するケース
上記に当てはまる場合は、目的を整理し、内製化が妥当と思われるタイミングで内製化を検討することが望ましいです。
それでは、上記2点の何が問題かを、詳しく見ていきましょう。
研修を内製化する目的が不明瞭なケース
研修の内製化を成功させるためには、明確な目的意識が不可欠です。
そもそも何のために研修を内製化するのかが明確でない場合、内製化のプロセス全体が混乱し、効果的な結果を得ることは困難となるでしょう。
目的が不明瞭であると、どの研修を内製化し、どの研修を外注すべきかの判断基準が曖昧になります。結果として、内製化すべきでない研修まで自社でおこなおうとしたり、逆に外部の専門知識を活用すべき場面で内製化を強行したりする可能性があります。
このような判断ミスは、研修の質の低下やリソースの無駄遣いにつながるでしょう。
さらに、明確な目的がないまま研修設計を進めると、その内容が一貫性を欠き、焦点がぼやけてしまう恐れがあります。
たとえば、評価スキルの向上を目指すべき研修が、一般的なリーダーシップ論に終始してしまうなど、本来の目的から逸脱する可能性があります。
このような場合、せっかく時間と労力をかけて内製化しても、結果的に意味のない、または効果の薄い研修となってしまうかもしれません。
したがって、内製化を検討する前に、組織として何を達成したいのか、どのような人材を育成したいのか、現状の課題は何かなどを明確にする必要があります。
この目的設定のプロセスを丁寧におこなうことで、内製化の方向性が定まり、効果的な研修プログラムの構築ができるようになるでしょう。
コストカットだけを目的として研修を内製化するケース
研修の内製化において、コスト削減のみを目的とするアプローチは推奨できません。確かに、経費節減は企業経営において重要な取り組みですが、それだけを理由に内製化を進めると、さまざまな問題が生じる可能性があります。
たとえば、コストカットのみに焦点を当てると、どの研修をどのような内容で内製化するべきかの判断基準が曖昧になりがちです。結果として、本来外部の専門知識を活用すべき分野まで安易に内製化してしまい、研修の質が低下する恐れがあります。
コスト削減を最優先すると、外部研修を一切利用しない選択肢に傾きやすくなるでしょう。しかし、自社内に十分な研修設計のノウハウがない場合、効果的な研修プログラムの構築は困難を極めます。
専門的知識や最新のトレンドを取り入れた質の高い研修を提供できず、結果的に従業員の能力開発や組織の競争力向上という本来の目的から離れてしまう可能性があるのです。
したがって、研修の内製化を検討する際は、コスト面だけでなく、研修の質、効果、自社の能力開発ニーズなど、多角的な視点から判断することが重要です。
場合によっては、一部の研修を外部委託しつつ、自社の強みを活かせる分野に特化して内製化を進めるなど、バランスの取れたアプローチが求められます。
効果的に研修を内製化する手順
研修の目的・目標を明確化する
研修を内製化する際は、まず研修の目的・目標を明確にし、計画を立てることから始めます。
まずは経営層や現場へのヒアリングなどを行いながら、組織内に潜む課題を顕在化し、研修テーマを明らかにします。
研修を効果的に実施するためには、どの能力をどの水準まで伸ばすべきかが明確に定義されていることが重要です。具体的には、組織内で「能力モデル」を明確化し、研修ではどの能力をどのレベルに達成させるのかといった明確な目標を設定しましょう。
目標を明確化することにより、研修の方向性が定まり、効果的なプログラムの設計が可能です。同時に、研修後の評価もより客観的に行えるようになり、継続的な改善にもつながります。また、参加者自身も研修を通じて何を強化しなければならないかが認識でき、より積極的に学習に取り組みやすくなるでしょう。
講師の選定
研修の目的が決まったら、次に講師の選定を行います。社内講師を選定する場合は、以下の条件を参考にするとよいでしょう。
- 研修内容に対する豊富な知識や経験がある
- 高いコミュニケーションスキルを身につけている
社内講師による研修を実施することのメリットの一つとして、業界特有の商習慣や俗人化してしまった業務遂行における実践的なノウハウを会社の財産として体系化・定着させることがあります。そのためにも、すでに豊富な知識や経験をもつベテラン社員を講師として選任し、自らがもつ知識やノウハウの棚卸をしてもらうと良いでしょう。
また、研修では、受講者に対して一方的に情報を伝えるのではなく、受講者が主体的に学べるような環境づくりも大切です。そのためには、研修講師が受講者に積極的に質問を投げかけ、ディスカッションを促したり、受講者のノンバーバルな反応にも細やかに気づき、その場で適切に対応することが必要です。講師がコミュニケーションスキルを高いレベルで身に付けることは、研修の質にも大いに影響するため、講師選定における判断基準の一つにするとよいでしょう。
ただし、人事部門は社内講師にすべてを丸投げするのではなく、講師としてのスキル向上につながるような機会を提供することも必要です。
研修プログラムの作成
研修講師が決まったら、研修プログラムやカリキュラムの作成を行います。効果的な研修を実施するためには、伸ばしたい能力の性質を理解し、それに適したアプローチを選択することがとても重要です。
例えば、知識の習得には、講義やeラーニングなどの座学が効果的です。スキル向上を目的とした研修では、座学だけでなく、ワークショップやロールプレイングなど実践・演習に取り組む時間を多く確保することが有効です。
具体的な準備の中には、研修で使用するテキストなどの作成も含まれるため、作成可能な期間を設けることも必要です。
研修の効果測定と改善
研修を実施した後は、当初計画した目標が達成できたのか、効果測定を行い、継続的に研修内容をブラッシュアップしていくことが大切です。
効果測定を適切に行うためには、きちんと研修の目的・目標を明確化しておくことが前提となります。効果測定の方法の一つとしてとしては、理解度テストや研修アンケートの実施があります。以下に、よく使用されるアンケートの設問例とその意図をご紹介します。
| 設問 | 回答形式 | 意図 |
|---|---|---|
| 1. 研修前にどんなことに悩んでいましたか? | 自由記述 | 参加者の受講前の状態を把握し、研修がニーズに合っていたかを評価する |
| 2. 研修の内容は、あなたの業務に役立つと思いますか? | 複数選択・自由記述 | 研修の実用性を把握する |
| 3. 研修を受けて、今日からどんな行動をしますか? | 自由記述 | 学んだ内容の実践意欲と具体的な行動計画を確認する |
| 4. 今回の研修を100点満点で評価すると何点ですか? | 数値入力 | 研修の全体的な満足度を定量的に測定する |
| 5. 講師の説明はわかりやすかったですか? | 5段階評価 | 講師のパフォーマンスを評価する |
| 7. 研修で最も印象に残った内容は何ですか? | 自由記述 | 特に効果的だった内容を特定し、今後の研修内容に反映する |
| 8. 研修の改善点や課題があれば教えてください | 自由記述 | 参加者視点からの具体的な改善案を収集する |
| 9. 今後受講したいテーマを教えてください | 複数選択・自由記述 | 今後の研修ニーズを把握し、研修計画に反映させる |
| 10. この研修を同僚にお勧めしたいと思いますか? | 複数選択・理由 | 研修の推奨度を評価する |
まとめ
研修の内製化は、自社の特性に合わせた効果的な研修を実現でき、コスト削減にもつながる可能性がある一方で、慎重な検討が必要です。
内製化を進める際には、目的を明確にし、自社のリソースと外部の専門知識をバランスよく活用するように注意しましょう。
すべての研修を内製化するのではなく、自社の強みを活かせる分野に特化し、普遍的な内容や最新トレンド、専門性の高い分野については外部研修を活用するなど、使い分けをしていくこともポイントです。
また、コスト削減だけを目的とした安易な内製化は避け、研修の質と効果を最優先に考えましょう。
適切な形で内製化を進めていければ、組織の人材育成を、費用対効果高く実施していけるはずです。
組織・人事プロフェッショナル養成講座を配信中!
人事制度を学んだことがない方向けに、企業における人事の役割を体系的に学べる講座をオンデマンド型で配信しております。
- 全10回の講座でどこよりも「深く」「幅広く」学べる
- 合計約900ページにも及ぶ資料をプレゼント
- オンラインでいつでもどこでも受講可能!
- 講師への質問が可能!
本講座では、人事に配属されたばかりの新人の方はもちろん、今の人事のやり方が正しいか今一つ自信が持てない経営者、人事責任者、人事コンサルタントを対象に、企業における人事精度を一から学ぶことができます。
記事監修

- 前田 正彦(まえだ まさひこ)
- 株式会社スキルアカデミー 代表取締役CEO
慶應義塾大学経済学部卒業。米国マサチューセッツ工科大学経営大学院(Sloan School of Management)修了。株式会社前田・アンド・アソシエイツ代表取締役(現職)。
株式会社NTTデータにて金融システムの開発に携わった後、 数々のコンサルティングファームにて、戦略立案から実行・定着までのプロジェクトを数多くリードしてきた。
その後人事・組織コンサルティングの必要性を痛感し、当該分野のプロジェクトを立ち上げ、戦略から人事・組織コンサルティングまで一貫したサービスを提供している。
スキルアカデミーにおいては、代表取締役CEOとしてAI人事4.0事業全体の推進をリードするほか、組織・人事・人材開発などの案件を数多くリードしている。
また組織診断・管理特性、職務等級制度・成果報酬制度などツールを開発。グローバル人事プロフェッショナル組織であるSHRM認定資格を取得。