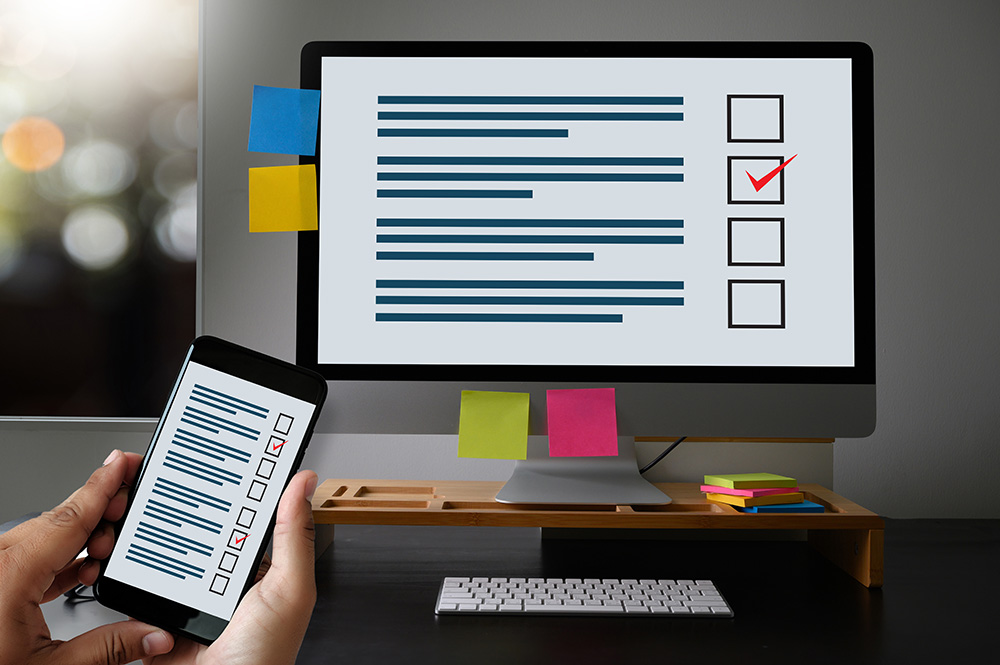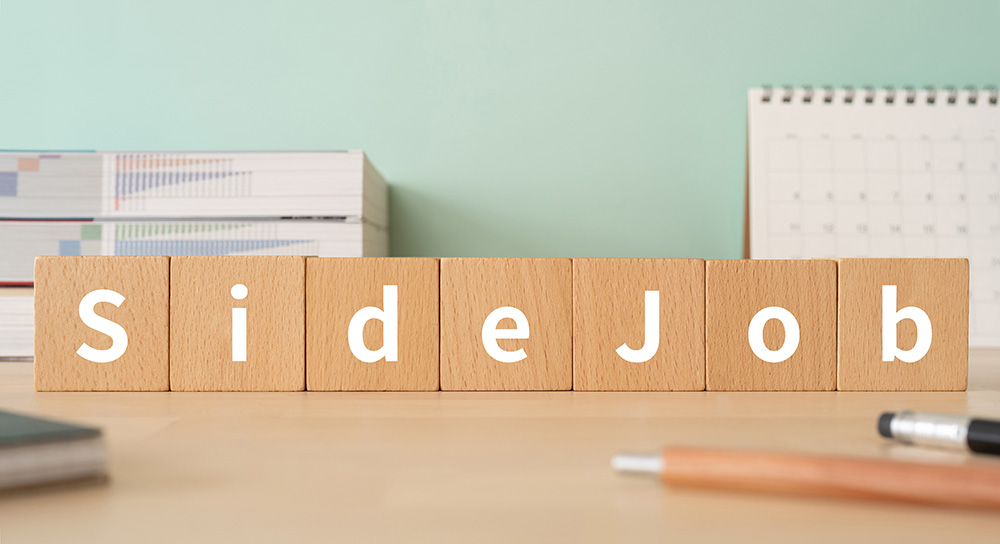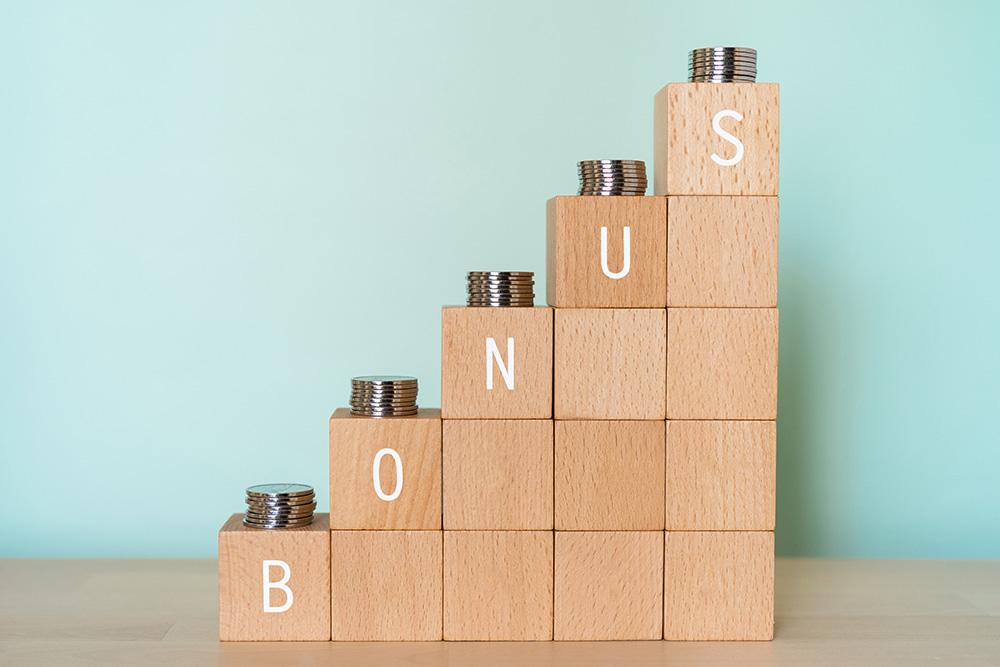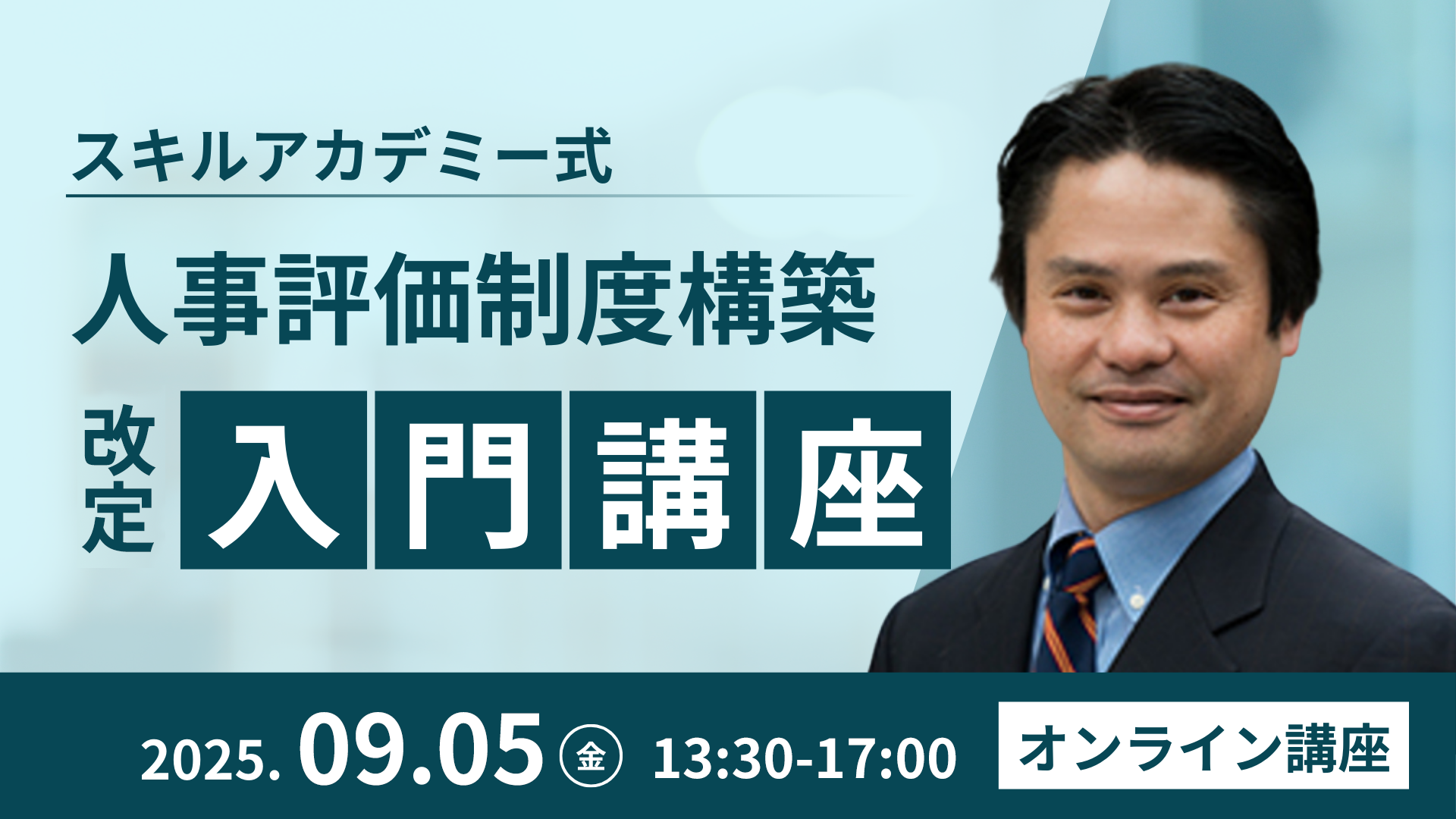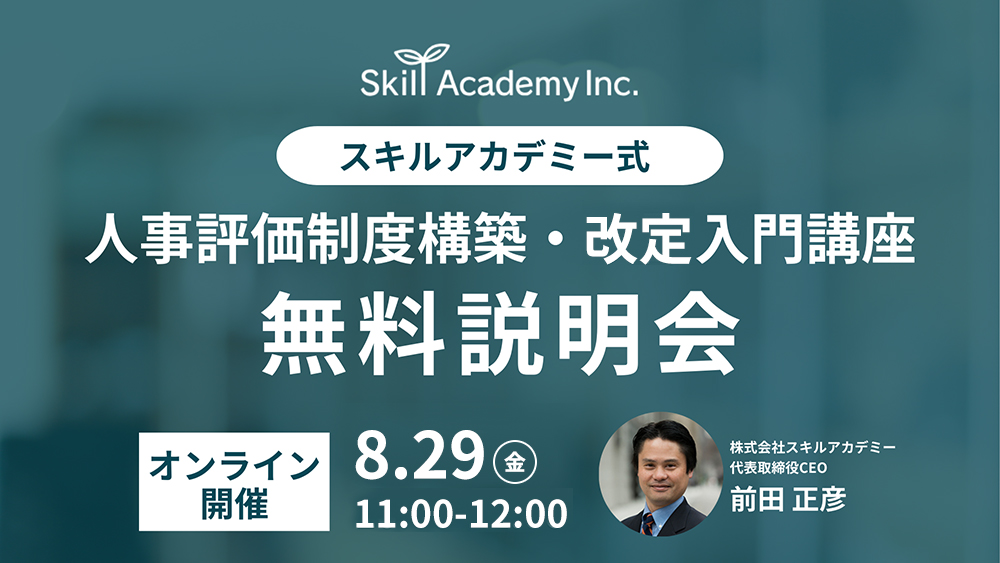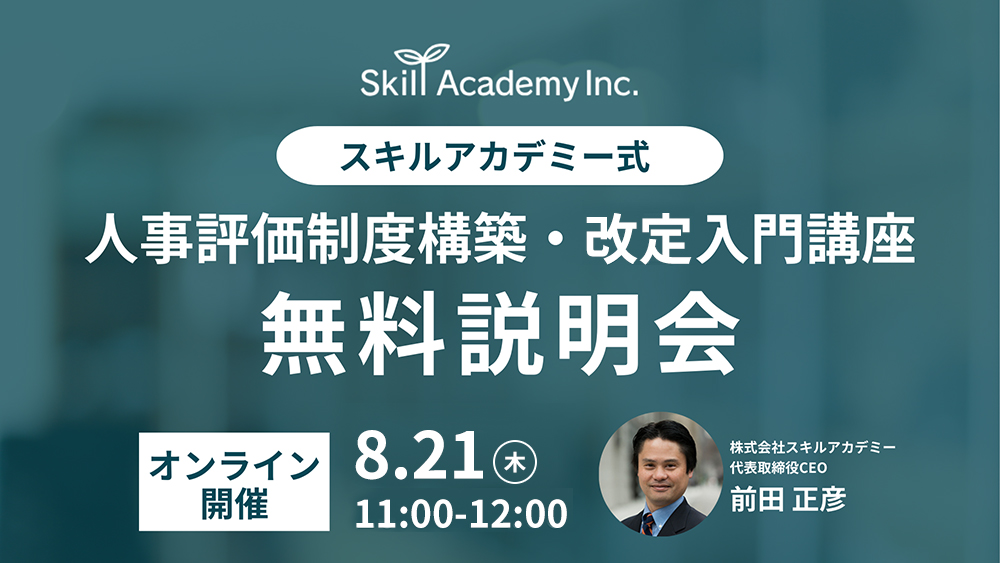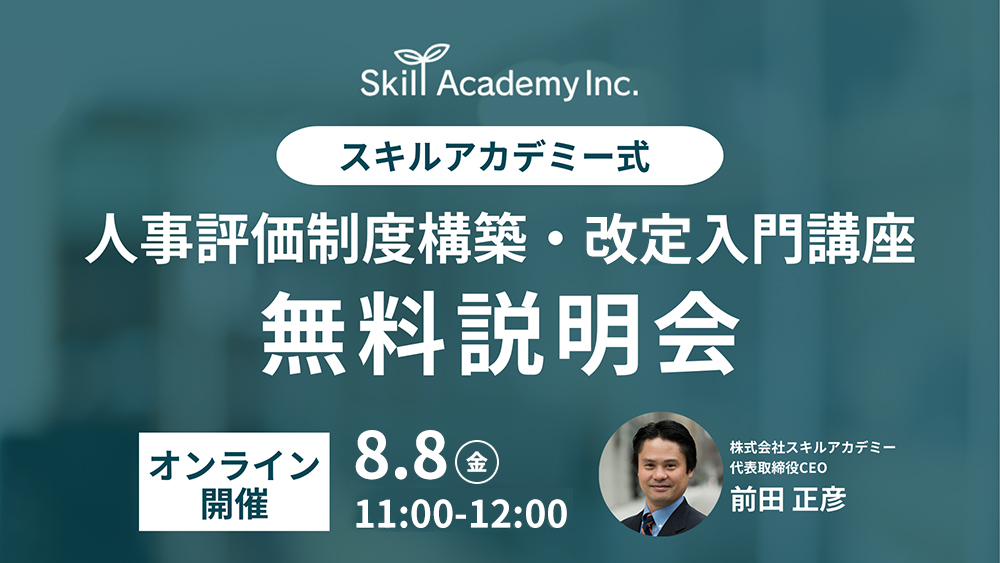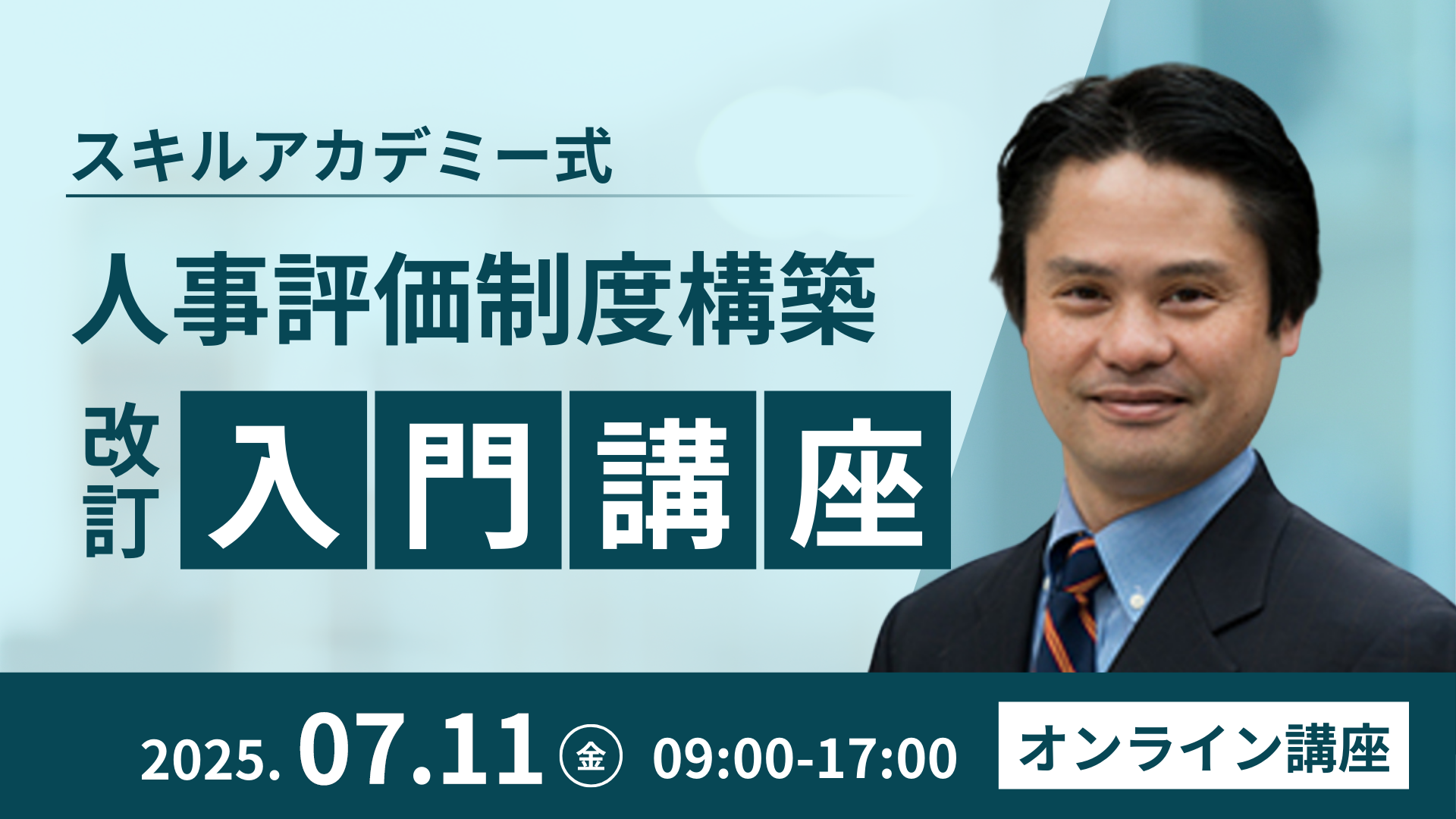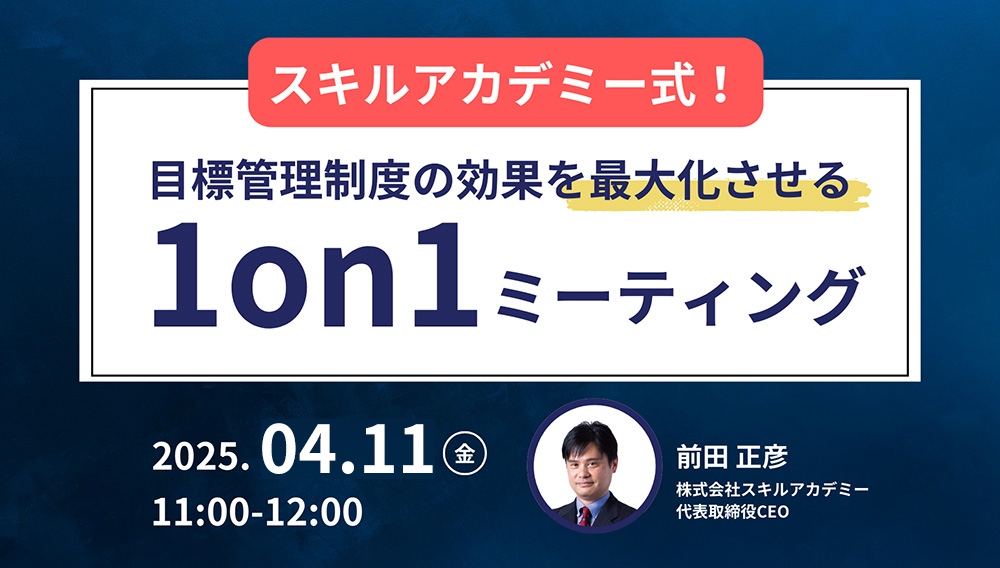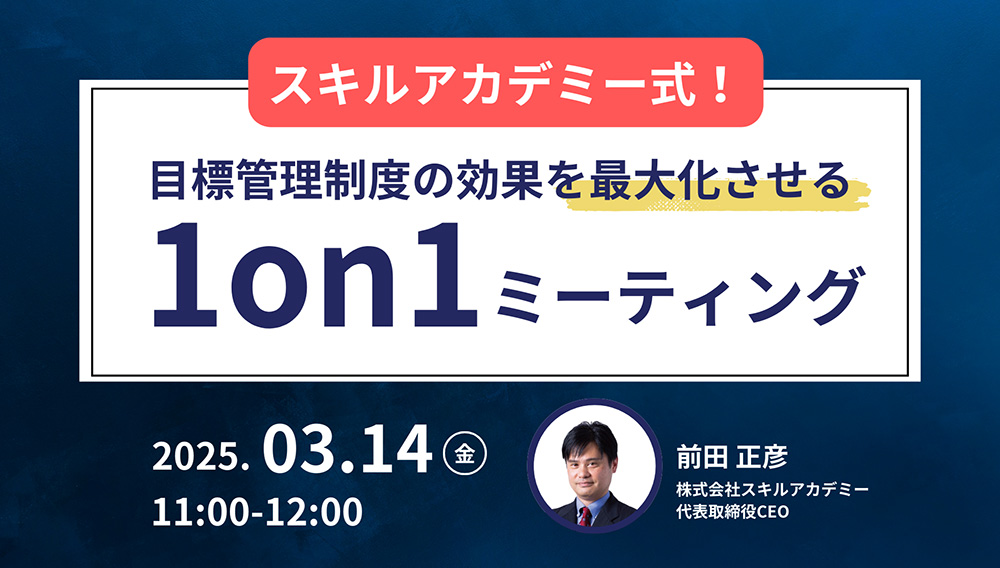人事コンテンツ
評価者研修とはどのようなもの?その目的やポイントから実施すべき企業の特徴まで徹底解説
2025/3/27

「人事評価の属人化により評価にばらつきが生じてしまっている」「評価の公平性を高め、社員の不満を解消したい」と悩む人事責任者の方も少なくないでしょう。
評価者研修は、こうした課題を解決するための有効な手段の1つとして注目されています。
本記事では、評価者研修の概要や実施の目的、公正な評価をおこなうためのポイントについて詳しく解説します。人事評価制度の改善を目指す人事責任者の方々にとって参考になるはずですので、ぜひ最後までお読みください。
評価者研修とは
評価者研修とは、人事評価を実施する評価者を対象としておこなわれる研修です。
評価者は、評価者研修を通じて、公平で効果的な人事評価をおこなうために必要な知識とスキルを習得します。
人事評価は、従業員のパフォーマンス向上や組織の成長に直結する重要な業務であるため、評価者研修は多くの企業で重要な役目を果たします。
評価者研修が適切に実施されると、公平な評価をおこなえるようになり、従業員のモチベーション向上や、ひいては組織全体の生産性向上にも期待できるでしょう。
評価者研修をおこなう目的
評価者研修には複数の目的がありますが、中でも以下の2つが代表的です。
- 公平な人事評価をおこなうため
- フィードバックの質を向上させるため
ここではそれぞれに関して詳しく解説します。
公平な人事評価をおこなうため
評価者研修の最も重要な目的は、公平な人事評価を実現することです。
研修を通じて、評価者には評価方法や評価基準に対する理解を深めてもらい、組織内における評価のばらつきを抑制することを目指します。
評価のばらつきとは、たとえば、ある評価者が部下を評価する際に、その部下との関係が良好であることなどから「よい」という評価をつけます。一方で、別の被評価者に対しては同レベルのパフォーマンスでありながらも「悪い」と評価してしまう状態のことです。
評価にばらつきが生じる背景には、そもそも適切な評価制度の設計ができていない点や、正しい評価方法や評価の考え方が、評価者に浸透していない点にあります。そうした組織では、人事評価の基準や評価方法など、個人によって違いが出やすくなります。
評価にばらつきがあると、従業員に不公平感や不満といった感情が生まれやすく、業務へのモチベーション低下や組織への不信感にもつながるでしょう。
そこで、こうした問題の解決に有効なのが評価者研修です。研修を通じて評価者に評価基準や評価方法について理解を深めてもらうことで、人事考課の足並みを揃えやすくなります。
それにより、従業員の不満が消えるだけでなく、会社の帰属意識の高まりや仕事の意欲の向上などにもつながり、組織全体の生産性向上にも期待できるでしょう。
フィードバックの質を向上させるため
評価者研修のもう1つの重要な目的は、フィードバックの質を向上させることです。評価者の役割は、単に評価をおこなうだけではありません。日常の業務において、部下や同僚の成長につながる効果的なフィードバックを提供することも、評価者の重要な責務です。
組織の成長につながる適切なフィードバックをおこなうためには、評価者が会社の方向性や目標を十分に理解することが必要です。その上で、個々の従業員の行動や成果が組織の目標達成にどのように貢献しているかを、的確に判断する能力が求められます。
評価者研修を通じて、評価制度の背景にある理念や目的、具体的な運用方法について評価者に深く理解してもらう機会を設けることで、評価者はより質の高いフィードバックをおこないやすくなるでしょう。
また研修では、建設的なフィードバックの手法や、部下の成長を促すコミュニケーション技術も学びます。それによって、日々の業務の中で、部下にタイムリーかつ的確なアドバイスや指導を評価者がおこなえるようになることも、評価者研修の利点です。
評価者研修を実施すべき企業の特徴
評価者研修は多くの企業にとって有益ですが、とくに以下のような特徴を持つ企業において、その実施が推奨されます。
- 評価の属人化が起きてしまっている
- 評価スキルが不足している評価者が多い企業
それぞれの詳細について解説します。
評価の属人化が起きてしまっている
評価の属人化が生じている企業は、評価者研修を実施すべきです。
評価の属人化が起きることで、同じ能力や成果を持つ従業員であっても、評価者によって評定に差が生じてしまいやすくなります。たとえば、ある部署では厳しい評価基準が適用される一方で、別の部署では比較的寛容な評価がおこなわれるという状況です。
このような評価の不一致は、低く評価されてしまった従業員に不公平感や不満を抱かせる原因となります。
また、評価の属人化は、評価者が異動などで職場から離れた際に、各従業員の評価が大きく変わる可能性があることも問題です。
こうした評価の属人化は、従業員のモチベーション低下や組織への不信感につながり、長期的には人材流出や組織のパフォーマンスの低下にもつながるでしょう。
このような問題の解決に役立つのが評価者研修です。研修を実施し、評価におけるバイアスや一般的な誤りについても学んでもらうことで、公平性と一貫性のある評価をおこないやすくなります。
評価スキルが不足している評価者が多い企業
評価者のスキル不足は、人事評価の効果を大きく損なう要因となり得ます。いくら洗練された人事制度が整備されていても、それを運用する評価者のスキルが不十分であれば、制度本来の機能を発揮することはできません。
評価者に求められるスキルは多岐にわたります。
適切な目標設定や効果的なフィードバック、公平な評価の実施など、これらのスキルは単に経験を積むだけでは十分に習得できるものではありません。
たとえば、目標設定においては、組織の目標と個人の目標を適切に連携させ、数値に基づいた実現可能な目標を立てることが重要です。また、フィードバックでは、建設的かつ具体的なアドバイスを提供し、部下の成長を促す技術も必要です。
評価者研修は、これらのスキルを体系的に学び、実践的に身につける絶好の機会となります。
研修では、ロールプレイングやケーススタディなどの手法を用いて、実際の評価場面を想定した訓練をおこないます。これにより評価者は、理論だけでなく実践的なスキルを培うことが可能です。
さらに、研修を通じて評価者同士が意見交換をおこなうことで、ベストプラクティスの共有や共通の課題に対する解決策の検討も可能となるでしょう。このような相互学習の機会は、組織全体の評価スキル向上に大きく貢献します。
評価者が公平な評価をおこなえるようにするためには
評価者が公平な評価をおこなうことは、組織の健全な発展と従業員の満足度の向上に不可欠です。評価の公平性を確保するためには、以下のようなポイントに気をつけましょう。
- 管理職に評価の狙いや全体像を理解してもらう
- 能力を評価する場合は会社が求める能力水準を明確にする
- JNDに基づき評価の基準を整える
- 直属の上司に最終評価決定権を与える
それぞれなぜ重要なのかについて、詳しく解説していきます。
管理職に評価の狙いや全体像を理解してもらう
評価者、とくに管理職がそもそも能力を評価する狙いや全体像を正確に把握できているかは、公平な評価をおこなう上で極めて重要です。評価者が評価制度の目的や組織全体の方向性を理解していなければ、適切な評価をおこなうことは難しくなります。
たとえば、会社が長期的な人材育成を重視しているにもかかわらず、評価者が短期的な成果のみに注目して評価をおこなってしまうと、組織の目標と評価結果にズレが生じてしまいます。
また、評価制度の全体像を理解していなければ、個々の評価項目の重要性や相互の関連性を適切に判断できず、バランスを欠いた評価になりかねません。
そこで、評価者研修などを通じて、評価の目的や全体像を徹底的に理解してもらうことが重要です。
具体的には、会社の経営理念や中長期的な戦略目標、それらと評価制度との関連性などを包括的に学ぶ機会を設けることが有効です。また、評価結果が従業員の育成や組織の発展にどのように活かされるのかについても理解を深めてもらいましょう。
このような取り組みにより、評価者は部下を評価する際に単に点数をつけるだけでなく、組織の目標達成に向けて評価し、育成する視点を持てます。結果として、より精度の高い公平な評価が可能となり、組織全体の成長につなげられるのです。
能力を評価する場合は会社が求める能力水準を明確にする
会社が求める能力水準を明確に定義することも、公平な能力評価をおこなう上で重要です。そもそも会社としてどの程度の能力を求めるのかが明確でなければ、評価を正しくおこなうことは困難といえるでしょう。
各職務においてどの水準の能力を求めるのかが明確でない場合、評価基準は評価者の主観によって大きく変動してしまいます。たとえば、ある評価者が「標準的」と考える能力レベルを、別の評価者は「優秀」と判断するかもしれません。
そのため、会社は職務ごとに具体的な能力要件を策定し、期待される行動や成果を明確に定義する必要があります。
たとえば、営業職であれば「月間の新規顧客のアポイント獲得数を10社以上にする」、プロジェクトマネージャーの場合は「予算内でプロジェクトを完遂させる」などが挙げられるでしょう。
これにより、評価者は共通の基準に基づいて評価でき、評価の一貫性と公平性が向上します。また、従業員にとっても自身の目標が明確になり、キャリア開発の指針ともなるのです。
JNDに基づき評価の基準を整える
評価のばらつきを最小限に抑えるためには、JND(最小可知差異)の原則を活用することが効果的です。JNDとは、人間が知覚できる最小の差異のことを指し、この原則を評価基準の設定に応用することで、より客観的で一貫性のある評価制度を構築できます。
具体的には、目に見える明確な差異が観察される境界線に評価基準を設けることで、能力を定量的に測定しやすくなります。
たとえば先述の営業職の例では、「新規顧客獲得数が5社未満」「5社以上10社未満」「10社以上」といった具合に目標の達成度合いをレベル分けするとよいです。そうすることで、評価者が能力・成果の違いを明確に認識できるようになります。
プロジェクトマネージャーの例の場合、「予算超過5%以上でプロジェクト完結」「予算内±5%でプロジェクト完結」などの基準を設けることで、パフォーマンスの違いを明確に区別できるでしょう。
このようにJNDの原則に基づいて評価基準を設定することで、評価者による主観的な判断の余地を減らせるため、より公平で一貫性のある評価をできるようになります。
なお、JNDの評価段階を細かく設定しすぎると、各段階の評価の違いがわかりづらくなるため、5段階程度に設定することが大切です。
直属の上司に最終評価決定権を与える
評価の公平性と正確性を高めるための方策としては、直属の上司に最終評価の決定権を与えることも有効です。
直属の上司に最終評価の決定権を付与することで、評価に対する責任感が強化されます。最終的な判断がほかの人材に委ねられる場合、「あとで別の人が決めるから」という認識から、評価に対する責任感が薄れてしまう可能性があるでしょう。一方で、最終決定権を持つことで、上司はより慎重かつ公正に評価をおこなえるようになります。
直属の上司は部下の日々の業務のパフォーマンスを最も近くで観察できる立場にあることも、上司に最終評価決定権を与える理由の1つです。
日ごろからパフォーマンスを近くで観察できるため、単発的な成果だけでなく一貫した努力や成長過程、チームへの貢献度など、数字には表れにくい要素も含めて総合的に評価できます。
営業職を例に挙げれば、営業成績だけでなく顧客との関係構築能力や社内での協調性なども考慮に入れた、より総合的な評価がおこなえるでしょう。
そのような側面においても、直属の上司に最終評価決定権を与えることが望ましいといえます。
ただし、このアプローチを採用する際も、評価者である直属の上司に対する研修と支援が不可欠です。評価スキルを高めるため、個人的なバイアスを排除して評価するための訓練が重要となります。
また、そもそも公正な評価をおこなえる人事制度を確立することも、決して欠かせない要素といえます。
しっかりと準備をした上で、直属の上司に最終評価決定権を与えることで、より正確で公平な評価をおこなえるようになるでしょう。
まとめ
公平で効果的な人事評価制度を構築する上では、評価者研修が有効です。とくに、評価の属人化や評価スキルの不足が見られる企業では、その重要性が高いでしょう。
しかし、評価者研修だけでは不十分です。会社が求める能力水準を明確にして評価基準を明らかにしたり、直属の上司に最終評価決定権を与えたりするなどの各種施策も極めて重要です。
本記事でご紹介した各種取り組みを多面的に実施することで、評価者間のばらつきを最小限に抑えられ、従業員からの信頼獲得や組織全体のパフォーマンス向上に期待できるでしょう。
組織・人事プロフェッショナル養成講座を配信中!
人事制度を学んだことがない方向けに、企業における人事の役割を体系的に学べる講座をオンデマンド型で配信しております。
- 全10回の講座でどこよりも「深く」「幅広く」学べる
- 合計約900ページにも及ぶ資料をプレゼント
- オンラインでいつでもどこでも受講可能!
- 講師への質問が可能!
本講座では、人事に配属されたばかりの新人の方はもちろん、今の人事のやり方が正しいか今一つ自信が持てない経営者、人事責任者、人事コンサルタントを対象に、企業における人事精度を一から学ぶことができます。
記事監修

- 前田 正彦(まえだ まさひこ)
- 株式会社スキルアカデミー 代表取締役CEO
慶應義塾大学経済学部卒業。米国マサチューセッツ工科大学経営大学院(Sloan School of Management)修了。株式会社前田・アンド・アソシエイツ代表取締役(現職)。
株式会社NTTデータにて金融システムの開発に携わった後、 数々のコンサルティングファームにて、戦略立案から実行・定着までのプロジェクトを数多くリードしてきた。
その後人事・組織コンサルティングの必要性を痛感し、当該分野のプロジェクトを立ち上げ、戦略から人事・組織コンサルティングまで一貫したサービスを提供している。
スキルアカデミーにおいては、代表取締役CEOとしてAI人事4.0事業全体の推進をリードするほか、組織・人事・人材開発などの案件を数多くリードしている。
また組織診断・管理特性、職務等級制度・成果報酬制度などツールを開発。グローバル人事プロフェッショナル組織であるSHRM認定資格を取得。